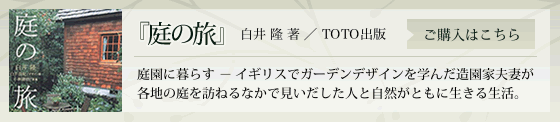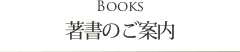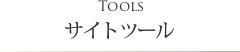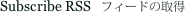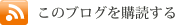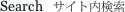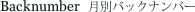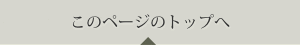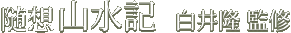十勝千年の森のこと
- 配信日
- 2018.06.26
- 記事カテゴリー:
- 第一巻 湖水地方レポート
■庭園を造る
「庭園を造る」のは、人が、自然と和解をする営みです。
人が自我をもつようになって、暮らしの場の都市化が進む過程で、人は、自然との闘争に明け暮れます。しかし、人が、成熟に向かおうと決意するとき、人は、自然の摂理との和解が必要だと悟るのです。人類の歴史も、個人の歴史も、その点は同じです。
人は、海に潜り、山に登り、旅をし、そして、庭園にたどりついて、自然との対話を始めるのです。
十勝毎日新聞社の林光繁社主が、北海道十勝に大庭園を作ろうと発起したのも、人の前に聳え君臨してきた北海道の自然に対し、何世代ものあいだ、歯を食いしばり耐え忍んで生きてきた人が抱く、和解への決意でした。それが、豊かさに向かう大きな試練だと悟り、この試練を誰かが引き受けなければならないという使命感からです。
■大庭園とはなにか・・・?
世界の大庭園の歴史を語ろうとすれば、大部の著作を必要としますが、ここでは、林光繁氏が十勝千年の森を構想する際に念頭に置いた、英国の大庭園を概観してみます。
歴史的に見れば、教会の庭、貴族の大庭園がありましたが、英国庭園と呼ばれる特徴が顕著になるのは、近代的な新興富裕層が作った大庭園です。英国を旅する人々は、一様に、その高度な庭園文化を称賛し、あこがれを抱きます。7つの海を支配した英国経済の頂点が1890年だとすれば、文化は経済の隆盛に10年遅れて花を開くと言われますから、英国文化の頂点は、20世紀初頭のエドワーディアン朝に訪れました。抬頭した新興富裕層は、世界中から稼いだ富をふんだんに注ぎ込み、その結果、贅をつくした無数の大庭園が生まれたのです。
■英国における庭園芸術家の系譜
高度な芸術の潮流が生まれる時には、意識の変化を荷なう施主と、その意識を具現化する芸術家が台頭します。19世紀の英国に興隆した、独自の庭園文化を支えた芸術家は、園芸家と、ランドスケープアーキテクトでした。
英国園芸界は、19世紀に「野草の庭」の魅力を世に問いかけたウィリアム・ロビンソン以来、西洋世界の園芸文化における先駆者として、革新と成熟を、綿々と積み重ねてきました。ロビンソン以前の園芸手法は、カーペットベディングと呼ばれ、分かりやすく言えば、花壇一面にパンジーを植え付けるようなものでしたが、ロビンソン以後、園芸芸術家は、色彩を複雑に構成し、植物同士の相性を調べ、自然風への模索が始まりました。
その営みは、21世紀に入ってもなお活発で、ニュー・ナチュラリズム/新自然主義と称される園芸手法に関する、さまざまな議論と試行錯誤が、今も行われています。
英国には、園芸とは別に、風景建築家/ランドスケープアーキテクトの系譜があります。それまで、フランス貴族の屋敷に作られた、整形式大庭園の影響下にあった英国は、19世紀の国力の増大とともに自信をつけ、抬頭した市民階級の富裕層は、自然との対話を求めました。その需要に応えるかたちで、ケイパビリティ・ブラウン等々、伝説的な芸術家たちが登場し、英国ランドスケープアーキテクトの系譜が生まれました。自然の風尚を楽しむ風景式庭園という、英国独自の庭園世界が誕生したのです。
イングリッシュガーデンという概念は、日本の通例では、花を楽しむ田舎家の庭/コテージガーデンを指します。日本庭園の伝統には、17世紀に造営された修学院離宮をはじめとして、古くから風景式庭園が造られてきましたから、英国の風景式庭園に新しい発見はなかったとも言えます。しかし、世界で一般的にイングリッシュガーデンとは、風景式庭園を意味し、世界にさきがけて誕生した英国の市民社会を象徴する様式として、公園の造形などに取り入れられました。ニューヨークのセントラルパークなどもその影響下にあります。長く生き続ける大庭園の様式は、その民族が共有する「自然観」の一部と化していくのです。
■十勝千年の森
しかし、21世紀初頭に、北海道で大庭園を造るという事業は、意味がまったく違います。経済、政治、文化、風土、すべての環境が異なる21世紀の北海道で、十勝の一知識人が「大庭園」を造るという意思の成就を、いったい誰が信じたでしょうか。途方もない計画です。この企図が成功すれば、それは、十勝の、あるいは、北海道の「自然観」を象徴する、あるいは、表現するものになるかもしれないのです。無から有を生むような、そんな大それたことを・・・と、多くの人々が冷ややかに見ていたのではないでしょうか。
■英国庭園文化との共同作業
デザイナーとして抜擢されたダン・ピアソン氏は、とても若い頃から、天才的な園芸家として知られ、英国園芸界の寵児でした。植物に対する圧倒的な深い知識と経験、そして、象形する技術水準の高さは、まったく群を抜いています。
メドウガーデンのメドウ/Meadowとは、「英国の」牧草地を意味します。盛夏に乾草を刈り取り、秋から冬にかけて家畜を放牧することで、家畜の蹄が土を耕して除草してくれるために、土は肥沃になり、支配力の強すぎる植物も減って、大小さまざまな野の花が咲き乱れるのに理想的な環境を作り出すのです。「英国の」とあえて形容詞をつけた理由は、日本の牧草地には、必ずしもそのままあてはまらないからです。
英国園芸界が、このメドウガーデンを愛してやまないのは、そこに人間の営為と自然の循環があって、手のかからない花の庭ができるという思いがあるからです。一年草の庭を作ろうとすれば、労力と費用が膨大で、小さな花壇を作るのが精一杯です。しかし、牧草地が、手をかけずに、人間と家畜と自然の循環によって、野の花の咲き乱れる花園になるというイメージは、「自然風」への志向とあいまって、園芸家の技術と見識を問う、素晴らしい魅力にあふれた世界観なのでしょう。
ピアソン氏は、その英国式園芸の伝統と歴史を知り尽くした上で、十勝清水の植物生態を把握し、高度な園芸的世界観を構築して、十勝千年の森のメドウガーデンを、西洋世界最高峰のメドウガーデンに昇華しました。
■アースガーデン
そこまでは、英国庭園とその園芸技術が培ってきた文脈の延長上にあったのです。
しかし、「アースガーデン」を、園芸という文脈上に位置づけることはできません。ピアソン氏は、園芸家から、英国ランドスケープアーキテクトの系譜に軸足を移して、この 困難な課題に立ち向かいました。十勝千年の森は、園芸界の頂点にあって、さらに存分に伸びしろのある、ダン・ピアソンという、とほうもない才能を手に入れたということになります。
「アースガーデン」は、日高の山々を風景の主題としていますが、それは借景という、数々の庭園に見られる手法の応用でもありません。目の前にそびえる山容から、不必要なものを捨て、その土地そのものが本来備えている美意識を、削り出す作業であったと思われます。この造形はあきらかに、古今東西の庭園史から逸脱し、あまりにも独創的でありながら、造形の精神として正統的であり、かつ、その様相は気品に満ち溢れています。人間の作為は身を潜め、生き物を生かす力を秘めた自然世界の、ストイックで厳格な骨格の表現であり、北海道の風景そのものにして、「日高の山々の美を畏怖すべし」と語らせている。これは、ピアソン氏デザイナー人生最高峰の仕事に間違いありません。
■アースガーデンと日本人の美意識
「十勝千年の森」を訪れた人々の多くが、「アースガーデン」の前にたたずんで言葉を失います。これほど、大胆で、かつ、本質的な庭園は、見たことがありません。洋の東西を超えて、このような庭園の傑作は、どこにも見当たらないのです。
このアースガーデンは、十勝千年の森成功の鍵となりました。
メドウガーデンは、園芸芸術家としてのピアソン氏のすべての野心を実現した、あるいは、英国園芸の粋を極めたと言えるほどの、水準の高さにありますが、英国園芸文化に、あまりにも深く根差しているために、必ずしも多くの日本人の心に届くものではないように見受けられます。
しかし、「アースガーデン」が表現する美意識は、日本人の美に対する嗜好にも、深く共鳴するものでした。西暦2000年にNHKが行った、日本人に最も愛されている美術作品のアンケートに、長谷川等伯の松林図が選ばれたことでも分かります。「不均整」、「簡素」、「枯高」、「自然」、「幽玄」、「脱俗」、「静寂」・・・これらは、日本が独自に育てた美意識を現すキーワードですが、そのまま、松林図に、そして、アースガーデンに当て嵌めて、齟齬がありません。奇跡的なアースガーデンの存在が、「十勝千年の森」の核心である所以です。
■傑作誕生の秘密
傑作誕生の秘密を、昭和の文芸評論家小林秀雄は、「無私の精神」にあるとしました。鍛錬を積み重ねた人に、ある日、「無私」の時間が訪れる、その間隙をついて、奇跡的な傑作が表出する。これは、芸術に限らず、人間世界すべての局面において共通する摂理です。
「アースガーデン」誕生の舞台にも、その奇跡的な創造を演出する大きな力が働きました。一介のデザイナーが担うことのできない、大きな力です。
映画「ラストエンペラー」の音楽をコンピュータで作り始めた坂本龍一氏に、映画監督ベルナルド・ベルトリッチは、「オーケストラにしてくれ」と命じ、坂本氏は「強制は常に正しい」と自らに言い聞かせて作曲を一からやり直しました。その結果、ベルトリッチは望み通りに映画作品の成功を手に入れ、坂本氏は新境地を拓いたのです。
十勝千年の森創造における総監督、林光繁氏は、十勝の言論をつかさどる新聞人として、北海道のオリジナル文化創造、そして、十勝のプライドと尊厳の刻印を切実に求めていました。「十勝千年の森」は、林光繁氏の人生を賭けた事業であり、しかも、気の遠くなるほど、難しい仕事です。
「この土地に大庭園を作れ」という途方もない強制があり、その設問を解くことを引き受けたデザイナーの無私の空隙に、奇跡の表出が生まれた。林光繁氏は、畢生の果実をここに成就し、ピアソン氏は間違いなく新境地を拓いたのでした。
次にあるのは、西洋社会における庭園芸術家の多くが金言とする、18世紀英国の詩人アレグザンダー・ポウプの言葉です。この言葉は、十勝千年の森「アースガーデン」にこそ、捧げるべきだろうと思います。
<すべてにおいて 潮の満ち干をも司る 大地の神の声に耳を傾けよ>
■十勝千年の森のその後
「北海道の美の高み」と呼べる風景を作り上げた十勝千年の森は、今後、どのような展開をしていくのでしょうか。
庭園都市計画家という、プランニングおよびデザインを仕事としてきた私は、その仕事の過程で常に、施主の実力が8割であると理解していました。次の仕事を取るために、「私の作品」として発信せざるを得ませんでしたが、いつも恥ずかしいような居心地の悪さを感じ続けてきました。成果の8割は施主が支配しているというのが、私の本音です。8割の創造者である十勝毎日新聞社の方々、そして、もしかしたら十勝の人々が、自分たちは、十勝千年の森で何を成し遂げたのかと問い直すこと、その問いを何度も反芻し、読み返し、見直し続ける作業を通して、自然観を共有することこそが、この大庭園事業の最大の果実であると言えます。文化国家の中で、大庭園とは常にそのような役割を果たしてきたからです。
また、庭園の革新というものは、施主の人格とともに成熟することを通して、人々の心に深く生き始めるものです。政争から逃れた、八条宮初代智仁親王と二代智忠親王の、心の鬱屈と遊びが、桂離宮に刻印されているように。そして、ヴィータの人生のドラマがシシングハースト城庭園に、血痕のように染みついているからこそ、人々はその造形の旋律に、心を震わせるのです。
そのためには、施主の林光繁氏はこの大庭園に暮らすべきだろうと思います。自らの思いを躊躇なく告白し、晩年の数十年と言う時間をこの土地に捧げることで、この北海道知識人の大庭園は、庭園として、さらに成熟の道をたどるはずです。
そこからさらに、十勝の風土に資する道を探るのであれば、この大庭園の一画に人々が暮らすコロニーを作り、その暮らしの風景を大庭園と重ね合わせながら、磨き上げ、成熟に向かうべきでしょう。
この「十勝千年の森」構想の出発点には、英国のコッツウォルズの、名もない人々が暮らす田園風景に対する感動がありました。日本のガーデニングが追いもとめる最終的な造形は、「人々が暮らす景色の美意識」を作り上げることにあるのではないでしょうか。茶人が井戸茶碗等を通して、作品的成功などとはまったく無縁の、「無私の精神」を生きる庶民の普段使いの道具の中に、崇高な美を発見したように、今を生きる私たちの暮らしの中にも、奇跡が造形の手を動かす空隙を見出すことができるはずです。その一つ一つを丹念にすくいあげ、磨きあげることで、誇らしく美しい暮らしの景色というものが生まれるでしょう。
人は、「庭園に暮らす」ように、暮らしたい。