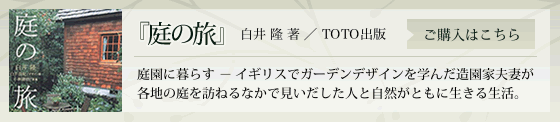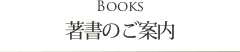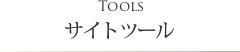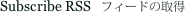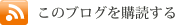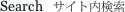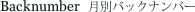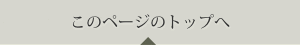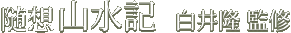私の父親は、義弘という名で、父親を6歳で亡くした。母子家庭で、貧しい農家の三男坊だから、学歴もなく、苦労と無理を重ねて生きた、難しい人物だった。47歳の時に、職場で転落死して一生を終えた。命綱が切れたのだという。
その年、私は13歳で、爾来、「運命」ということを深く考えることになった。
後年、仕事でご一緒した10年ほど年長の人物は、私の死んだ父親と印象が似ていて、これからどうやって年齢を重ねて行くのだろうかと、はたから見ていても不安をぬぐえない印象があった。名前が義弘で、6歳で父親を亡くしたという。長くお付き合いすることはなかったが、その人物はのちに、ビルの屋上から飛び降り自殺した。享年47歳であった。
名前、父親を亡くした年齢、享年、死に方、これらが一致する。そして、私に縁がある。類は友を呼ぶとも少し違うかもしれないが、不思議な符合だ。
「運命を信じている」と言う人がいる。人は、人の考えだけで生きているのではなくて、人の力を超えた、不思議な力に動かされていることを信じる、というほどの意味だろう。
運の良し悪しというが、命に係わるほどの運を、命を運ぶと書いて運命という。信じると信じないとにかかわらず、運命は、向こうから襲い掛かってくる。
人は、運命の手のうちに生きている。
その運命を動かしているのは、自然の力だ。
人は、その自然の力の理を知りたいと願う。
自然の理とは、自然が、この宇宙で、何をしようとしているのか・・・
自然生態学を通して、人が学んだことは、身の回りの緑の自然は、ブルドーザー1台あれば一瞬のうちに破壊し尽くすことができるけれど、自然の力は常に動いていて、数百年後には自然林が復活する、つまり、完璧な自然が再生するということだ。
畑に作物が育つのも、海で魚が採れるのも、この自然の力があるからだ。悪も、狂気も、長い時間のなかで淘汰される、それも、同じ自然の力のなせる業だ。そして、その自然の力が、命を運んでいる、つまり、運命を支配している。
小林秀雄が言う「無私の精神」、「頭の中の龍を殺せ」、禅の言う「無」・・・人は、狂った自我を正して、自然な人柄の成就を求めてきた。
自然は、人の運命を支配して、自然を成就しようとしている。人の心、つまり、人の考え方の中にある、悪や狂気を淘汰し、瑕疵を修正して、自然な状態を実現しようとしている。それが、一人一人に結果として運命の形で現れる。その理が、「道理」ということだろう。
道理を悟り、道理に従う・・私たちがすべき努力は、日々、道理を悟る心がけを怠らぬこと。
自然が人に求めているのは、この一点に尽きるのではないか。
Prepare for the Just War/正義の戦争に備えよ
- 配信日
- 2019.05.26
- 記事カテゴリー:
- 第四巻 自然万象
「Prepare for the Just War/正義の戦争に備えよ」・・・これは、1991年1月16日、イブニングスタンダード紙/Evening Standardのヘッドラインに大きく踊った活字である。私は35歳で、ロンドンに暮らしていた。午後3時には夜のとばりがおりる憂鬱な冬の日々に、米英仏を軸に、湾岸戦争の準備が進んでいることは分かっていた。チェルシー地区の夕暮れの街角である。ニューススタンドに積み上げられた新聞にこの文言を見つけた時、私は思わず自分の目を疑った。英国で数百年の歴史を誇る、権威ある夕刊紙の「正義の戦争」という言葉に、深く動揺したのだ。
翌日、湾岸戦争は開戦し、空爆の映像がテレビを通して同時中継された。
日本のテレビ局スタッフは、受話器の向こうで、興奮を抑えきれない様子だった。「おい見てるか・・・? これこそ、テレビショーだ。数千億円の出費なんか安いものだよ」。
香港で活動している中国人舞台演出家は、「オレは無力感に襲われている」と、書きなぐったファックスを流してきた。
私自身は、湾岸戦争にどんな感情も持たなかった。よく理解できなかったのだ。しかし、「正義の戦争」という文言に当惑した内心の動揺は、それ以後、私の脳裏の一角を確かに支配し続けた。この文言に対する、強い違和感は、何だったのか・・・?
平和憲法下、戦後教育を受けてきた私たちは、「すべての戦争は悪である」と考えるようになった。平和主義が、明るい未来への希望に満ちた先進的な思想であると信じてきたのだ。「正義の戦争」、あるいは、「聖戦」などという言葉は、1945年8月をもって、地上から消えてなくなった筈だったのである。しかしそれは、戦後を生きてきた日本人の内心の物語であって、日本以外の世界では堂々と胸を張って生き続けている。試しに、「The Just War/正義の戦争」をインターネットで検索してみるとよい。中東で、南北アメリカで、欧州で、ロシアで、アフリカで、ありとあらゆる正義の士が、明日の戦争を準備しているのだから。
実質的には戦後の日本だって、米国を通して、世界の戦争に加担してきた。間接的ではあっても、多くの民の命を奪い、暮らしを破壊し、その国家経済から収奪してきたのだ。朝鮮戦争特需で戦後復興に勢いをつけ、日米同盟を締結している米国は、横須賀や沖縄からベトナムへ、あるいは中近東へ、爆撃機を発進させてきた。そして、今度は湾岸戦争の戦費として日本が多額の費用を負担したのだ。日本が潔白であるなどとは、口が裂けても言えない。
それでも、「すべての戦争が悪である」という思想は、私たちの血肉と化している。憲法9条改訂を主張する人々が、私たち日本人のこの矛盾を指して、「平和ボケ」と揶揄する。戦争放棄の憲法と同様に、世界政治の現実を見ようとしない、幼稚な思想だというのである。
それは、本当だろうか・・・?
私は、この「平和ボケ」という表現に触れるたびに、The Just War/正義の戦争という活字と、内心にこびりついた、あの当惑を思い起こす。紛れもなく、この当惑は、戦後、平和憲法が育てた心性である。日本を取り囲む、ロシア、中国、米国の世界戦略を、北朝鮮の動向を、正視しなければならないことは当然だ。その事態に対する一定の備えも、現実に必要だろう。だからと言って、大多数の日本国民がもっている「すべての戦争は悪である」という思想は、大きな矛盾なのだろうか・・・この思想を日本人に植え付け、育てた、憲法9条を改訂しなければならないという解は、正しいのだろうか・・・
日本がどれほどの軍拡をしたところで、米国、中国、ロシア、どの国に対しても、戦争をしたら勝てない。だから、世界最大の軍事大国である米国の同盟国として保身をはかる。全世界のすべての国々が結束して戦っても勝てないほどの、とてつもない武力を、米国は保持しているという。はっきりしていることは、この憲法があると、同盟国である米国が行う戦争に、現実的な戦力として参加しにくい。いざという時に、捨て石にされないためにも、米国の同盟国として相応の立場を築く必要がある。だから、9条を改訂して、戦争ができる憲法を確立する必要がある・・・そんな論法だ。
だが、米国が負けないという保証は、ない。
中曽根康弘元首相は、日本は不沈空母であると、レーガン元大統領に胸を張った。米国が極東戦略上の理由で、中国、北朝鮮、ロシアと戦争をする際には、日本が不沈空母として最前線に立つ、という意味だ。言い換えれば、米国に忠誠を誓った。米国との戦争において、中国、北朝鮮、ロシアが勝つ確率は、米国が勝つ確率よりも低い・・・要するに確率論に国民の命を懸けた。
岡崎久彦は、アングロサクソンは歴史上、比較的、同盟国を裏切らないという理由で、アングロサクソンとの軍事同盟を推奨した。しかし、よしんばアングロサクソンが裏切らなかったとしても、アングロサクソンが負ける戦争は、どうするのか。アングロサクソンが負けそうになったら、戦争の途中で寝返って勝馬に乗るのか。アングロサクソンが負ける戦争では、日本が真っ先に壊滅するシナリオについて、岡崎久彦は言及しなかった。
北朝鮮が積み重ねている戦略を凝視し、中東が米国に対して抱く強い怨念を知るにつれて、私たちは、米国の強大な武力の優位性を疑い始めている。「抑止力」という言葉の響きに魅力を感じている人々も多いが、米国の武力は抑止が目的なのではなく、自国の防衛と富の略奪を目的としている。戦争が公共工事なのだから、有権者の歓心を買うために、その武力は必ず発動する。しかも、今や、泣き寝入りする気はないと、北朝鮮もイランも訴えているのだ。ベトナム戦争の結末も忘れてはならない。要点は、必ず起こる武力衝突に対する対処だ。安倍晋三首相が懸命にトランプ大統領に取り入る姿に、不安を感じている国民は、決して少なくないはずだ。戦争になれば、強大な武力を持つ米国が勝つ確率が高いという確率論は、どうやら有効ではないな、と。
しかし、今、米国を裏切って離反し、米国の極東戦略を後退させるような振る舞いに出れば、日本は、赤子の手をひねるよりも簡単に、貧苦に喘ぐことになるだろう。ロシアが日本に軍事的な拠点を作り、太平洋における覇権に参加するリスクを考えたなら、米国が、その圧倒的な軍事力を駆使して、日本を占領することだって考えられる。少なくとも、GO WESTと称する西進運動が、独立王国であったハワイを略奪したように、かつて琉球王国であった沖縄を、極東覇権の要塞として占有しようとするだろう。
総合的に考えれば、日本は米国の軍事力に積極的に加担して、世界を支配する強者のグループの一員として生きることを考えるしか、他に道はないじゃないか。二度と第二次世界大戦の失敗の轍を踏まぬように、人智を尽くす・・・だいたいのところ、安倍政権は、こう考えている。
ここまでは「人智」である。
だが、私たちは知っている。日本の地理的な条件を考えた場合、武力衝突が起きれば、米国と組もうが、中国、ロシアと組もうが、私たちは常に最前線に位置し、危険に晒される、戦争に巻き込まれれば、日本は風前の灯火である。1945年に、日本国民は、それを悟っていた。その結果として、日本国民は、「道理」に活路を見出す選択をしたのである。それが、日本国憲法だ。武力による問題解決を放棄して、道理に賭けた。
人事を尽くして天命を待つとは、この世を生きる方程式である。
天命が、人智を超えた天の采配であって、抗うことのできぬ強大な力であることを、私たちは知っている。天命が依拠する規範は、自然の道理であり、自然の摂理である。自然社会では、悪と狂気は、長い時間のなかで淘汰される。自然支配の原則である。「すべての戦争は悪である」は、善に照らして、誤っているだろうか・・・ボケているのだろうか・・・?
否、である。
自国の繁栄を維持するために、他国を脅迫し、破壊し、殺戮し、略奪することを「正義の戦争」と称することは、善に照らして、受け入れられるだろうか・・・
否。
戦後、私たちが理解したのは、そのことである。憲法9条の選択によって、私たちは、天命に賭け放したのだった。その証拠として、日米安保闘争はあったが、日本国憲法に反対する国民的闘争はまったくなかった。日本国民は、この憲法を歓迎して受け入れたのだ。そして、憲法9条が育てた日本人の思想は、自然の規範に照らして、世界に優越している。私たちは、この優位性を堅持しなければならないのだ。
一人の人間に置き換えた場合、暴力と殺人は悪だが、やむをえぬ正当防衛は許される。正当防衛となる事態に備えて、ハンドバッグの中に護身用の道具を忍ばせることも可能だ。だが、暴力と殺人が悪であるという思想を退ける理由にはならない。「正義の暴力」も、「正義の殺人」もありえない。世間には、暴力衝動と、殺人衝動に駆りたてられた人物がいる可能性はあって、そんな人物に遭遇する事態に備える必要はあるかもしれないが、だからといって、思想として、「正義の暴力」も、「正義の殺人」も、成立はしない。
国家に立ち戻った場合でも、正当防衛が必要な事態もありうるから、最低限の自衛戦力としての自衛隊は許容した。確かに、世界から暴力と戦争を駆逐することは不可能に思える。だが、「正義の戦争などありえない」という思想は守り育て、自然の摂理の掌中にとどまる努力を怠るべきではない。「正義の戦争も、時と場合によっては許される」という思想に転向することは、自然の摂理を前にして、人として、国家として、堕落である。
大切なポイントは、自然の規範がこの世界を支配している事実を、信じられるかどうかにかかっている。自然の規範が、どんな武力をもってしても立ち向かえぬ、有無を言わせぬ強大な力であること、宇宙の星々をも動かす摂理であることを、悟りきれるか・・・
しかし、戦争は、善をも破壊するじゃないか、自然が悪を淘汰するのを待っている間に、日本が滅ぼされるのが関の山だと主張する人々の声は、大きくて強い。近代兵器の強大な武力は、善悪の彼岸である、と。
力の論理しか信じない人々は、文字通り「力づく」で、国民の平和憲法に対する信頼を、くつがえそうとしている。帝国主義者が、狡知と脅迫で、相手を意のままに操ろうとするように、日本国民の民意を誘導しようと、たゆまぬ働きかけを続けている。
20世紀初頭に、ドイツの哲学者は、神の死を宣告し、近代が善悪の彼岸にあることを著述したが、爾来、先進諸国はその文脈に沿って1世紀余りの歴史を積み上げてきた、日本だけがそこから免れることはできないのだ・・・と。
本当に、そうか・・・?
否、天命を動かす自然の摂理は、善悪を峻別する。そして、自然の力は、すべての人間の力を凌駕する。周囲の暴力と狂気から身を守るために、私たち日本国民は、憲法9条を以て、この天命に賭けた。この道しかない、と。
米国の同盟国であろうが、先制攻撃が可能であろうが、戦争に巻き込まれれば、現代の強力な軍事状況下では、日本は、文字通り「壊滅的な被害」を免れない。リスクを減らすために人智を尽くすことは言うまでもないが、同時に、自然の摂理に対する立ち位置として、日本が世界のなかで飛びぬけて優位な立場にある現状を堅持すべきだ。「すべての戦争は悪である」との思想を根強く持つ戦後日本人の心は、自然の摂理にかなう。この思想は、憲法9条によって培われてきたのだ。戦後日本の、かけがえのない宝ものを投げ出すような愚は、夢にも、犯してはならない。
自然の詞・自然の規範
- 配信日
- 2019.03.31
- 記事カテゴリー:
- 序 はじめに
私は、2009年、53歳の時に、北海道の道東海岸に移住した。今は、太平洋に面した高台に暮らして湖水地方牧場を経営し、海岸草原のブラウンスイスと、湿原のイタリア水牛の2系統酪農で、チーズやヨーグルトの乳製品を製造・出荷している。一方で、社団法人湿原研究所の代表理事を務め、地域の自治体、民間企業等と連携して、自然博物館設立準備中だ。かつてなく、充実した日々を送っている。
しばしば、ここに至る経緯を、尋ねられるので、ここに記して、随想山水記の「序 はじめに」に、代えさせていただこうと思う。
最初に触れなければならないのは、35歳の時に、鎌倉材木座の富士和教会で神の使者を知ったことだ。こう書くと、大病や貧苦の不幸に出会って、新興宗教にはまったのだろうと考えるかもしれない。だが、そうではない。
私は20代にドキュメンタリストとして内外の取材に明け暮れたころ、新興宗教の取材をしたことがあるが、冨士和教会とはそうしたものではない。
職業の都市計画家として、2016年まで、中国禅宗第一位の径山萬壽寺復興計画に、監修者の立場で従事して、旧来の宗教にも比較的深く触れてきたが、それも違う。
「胸に手を当ててよく考えてみなさい」とは、子供を諭す時に親が言う言葉。内心の話だが、私は子供のころ、いつも胸に問いかけて様々な言葉を見つけた。そこで得た言葉が、世界を支配している規範であることを知っていたのだが、自我が発達する思春期には、その言葉を探し当てることができなくなったのだ。
「小さいころは神様がいて」とは歌の文句だけれど、本当にそうだと思いながら、それ以後もいつも、世界を支配しているはずの言葉の出自を探していた。万巻の書に触れ、博物館美術館劇場に足を運び、旅に明け暮れ、できるだけ多くの人に会い続けた。しかし、その言葉は見いだせなかった。富士和教会は、ようやく探し当てた、その答えだったのだ。
神の使者は、神の詞を伝えていた。そして、変節を積み重ねた人の思考が、頑固な自我でがんじがらめになっている、その心を、自然な道理の世界に導きだす指導をする教育者だ。運命を変えて、幸福への道に導く。指導を受ける人が、謙虚な心を取り戻すことが絶対条件だが、それにしても、そんな指導ができる人は、おそらく、人類史上存在しなかった。なによりも、神が直接手を下して作られた唯一の教会である。私は大いに感服してご指導を受けた。広く社会を知り、しかし、まだ自己が固まりきってはいない30代半ばの体験として、それは、格別に素晴らしい。本当に恵まれていたと思う。私の今の人生は、すべて、そこから始まったのだ。
私は、慶應義塾の経済を出て最初に、縁があって映画「戦場のメリークリスマス」の美術担当ラインプロデューサーの仕事についた。それは、人が生きる物語の舞台を作る、視覚的にはその「風景」を作る仕事だ。
その後、20代にはいろいろな仕事を引き受けて遊んだ。
フジテレビのバラエティ作家も良い経験だったし、モスクワに15歳のエフゲニー・キーシンを取材して、チャイコフスキー記念音楽堂で弾くピアノコンチェルトを聴いたのもこのころのことだ。ニューヨークでは、NYUに籍を置いて、今も路上でアルトサックスを吹き続けているbopperイズル・アズマとアパートをシェアし、夜の街をジャズを求めて歩き回った。「ジョーズ」や「オールザットジャズ」に主演した俳優のロイ・シャイダーの知己を得て、共同で映画プロデュースをして冒険の羽を伸ばしたのも、このニューヨーク時代のことだ。
その流れで、ドキュメンタリストとしてアメリカの会社から「日本の肖像」という4時間ドキュメンタリー演出の依頼を受け、腰を据えて2年間を費やした。アトランタで行った試写では、会社の担当者として全権を握るエグゼキュティヴプロデューサーが、「日本は、お巡りさんが子供たちとお遊戯をして遊ぶ国だ。そんなエピソードを追加してもらいたい」と、無理難題を押し付けて来た。その人物は、企画の当初からそのように主張していて、バカバカしいと無視してきたつけが、ここに来て反乱を起こしたわけだ。どんな努力を費やしても、くつがえせなかった。万事休す、である。若者に年収4千万円を出すビジネスの内情はこんなものだった。
「戦場のメリークリスマス」、「ラストエンペラー」などをプロデュースした英国人ジェレミー・トーマスは、私より6歳年上の兄貴分だ。私がアトランタからニューヨークに戻り、友人宅に居候しているところに、ロンドンから電話を寄越した。これからハリウッドに行くから遊びに来ないかと。サンタモニカのシャングリラに荷物をおろして向かったベル・エアーで、ジェレミーは、ハリウッドの配給会社が、「ラストエンペラー」の興行収益を、契約通りに払わないので法廷に訴えたのだと言った。
「昨日はサカモト、今日はタカシだ。Japan Weekだな」と笑うジェレミーに、お茶をいただきながら愚痴をこぼした。すると、「ユリーカ」という映画をハリウッドと共同製作した時に、同じことがあったと話してくれた。アメリカ人プロデューサーの注文を、監督のニコラス・ローグが受け入れられず、編集権を握るハリウッドがずたずたに改変した。ニコラス・ローグはその後、映画を作れなくなってしまった。編集権は人格権なのだ。アメリカはいつもこんな感じだ、と。
アメリカは散々だった。他にも、背筋がぞっとするようなことが、幾つもあったのだ。それ以後、一度もアメリカ合衆国の土を踏んでいないのだから、よほど懲りた。
ベルエアの別れ際にジェレミーは言った。「オレは強い、お前も強くなれ」。その後、ハリウッドの情報誌に、「トーマス氏が訴訟に勝訴した」との記事が掲載された。彼は今も、美しく才能あふれる映画を、一年に一作ずつ製作し続けている。
ちょうどそのころ、2017年にノーベル賞を受賞して脚光を浴びているイシグロカズオ原作「浮世の画家」を、監督として映画化しないかという誘いを受け、英国に移り住んだ。
「日本の肖像」は完成して全米に放映されたが、私は見なかった。件のアメリカ人プロデューサーが、日本に出かけていき、例の「おまわりさんのエピソード」を撮影して、全面的に再編集したと聞いたからだ。しかし、Directorとして、私のクレジットは残っている。アメリカに住む心ある人々は私を慰めたけれど、心無い人々は「とても素晴らしい作品だ」とお追従を言った。
ロンドンでは、早朝から脚本を書き始めて、疲れ果てる午後には、町に出て遊んだ。ニューヨークやハリウッドのホテルに滞在して、ビジネスミーティングに明け暮れる日々のたかぶった気持が、見る間に色あせていった。アメリカの日々は「闘い」だったが、ロンドンには「暮らし」があった。傷みつけられた心身が癒されていく。近所にあるスタジアムで、サッカーのある晩は決まって、チェルシーの応援歌が夜空に響き渡った。試合終了後の横町のパブでは、猛り狂ったフーリガンたちが、ビールで興奮を冷やしていた。
アメリカの仕事は小金を残したから、家内の白井温紀は、英国で一番授業料の高いカレッジを選んで、ガーデンデザインを学んだ。白井温紀は、90年代から21世紀初頭のガーデニングブームに乗り、NHKの番組の常連出演者として15年くらいはその仕事を楽しんだのだった。
英国では、少々規模が大きな開発計画は、ランドスケープ・アーキテクトがグランドデザインをつかさどり、インテリアデザイナー、建築デザイナー、ガーデンデザイナーなど、様々なデザイナーを指名して細部の設計を分担する。建築は、「近代」そのものだ。工学と美学の語法で、世界のすべての課題に立ち向かう。膨大なお金が動くから脚光を浴びる。
フランシス・ベーコンは、人間が自然を支配するのだと書いた。西洋で困惑したのは、人が自然を支配していると、誰もが信じて疑わないことだ。その思想が、西洋近代を爆発的に進歩させた原動力だった。しかし、私の内心の言葉によれば、この世を支配しているのは自然の力だった。フランス新哲学派の若者たちが、ノイローゼになりながら、ロゴス中心主義に回し蹴りを ! と語っていたことを、いつも思い出した。ランドスケープ・アーキテクトとして、自然と人間を取り持つ仕事ができるのではないか・・・。ロンドンでは、そんなことを、ふわふわと考えていた。
そんな日々の中で、あの内心の言葉がよみがえったのだ。
探し続けてきたのは、内心の言葉だったが、現れたのは脳裏の声だった。夜明けに覚醒しつつある頃、その声は、「丸くやるんだ」と言った。翌朝には、「優しくするんだ」と。反発するアメリカ人スタッフの扱いに疲れ果てていた時期だった。素直に受け止めたが、しかし、脳裏の声には困惑した。それに、「丸くやる」なんて、私の語彙にはまったくないものだった。いったいどうしたことだろう・・・。内省が始まった。一生、英国で暮らそうと考えていたのに、無性に日本に帰りたくなった。
脚本が完成するや、急いで日本に帰ると、待ち受けていたように、幼馴染が、私が会うべき人が鎌倉にいると言う。案内を乞うてお目にかかったのが、富士和教会の神の使者だ。私の問いかけに対してその老婦人は、「神様は、丸くやるんですよ、とか、優しくするんですよ、と、いつも言っているからね」と答えた。私は、あいた口がふさがらなかった。
神の使者は、私が探し求めてきた内心の言葉を、口頭で語っていた。だが、探し求めた内心の言葉を、人が私に向かって語り掛けると言う経験は、即座には受け入れがたいものだった。それでも気になってしかたがなくて、それから1年半の間、週に何度も訪ねて確かめたが、その人の「言葉」は、私が探し求めてきた内心の言葉と酷似していた。たくさんの不思議なことが身に降りかかってきて、だんだん、それらが、使者の言うことと因果関係があることが分かってきた。その人は、どこからどう見ても本物の神の使者だったのだ。
大学の恩師が言った。
「神が実在するのは、当たり前のことだ。誰が間に立つか、それが人類最大の設問なのだが、本物だと思える人物に出会ったということは、大変なことだ。ついて行くべきだ。」
問いかけと、傾聴と、内省の日々が始まった。鏡の前のガマガエルか、はたまた、標本箱に虫ピンでとめられた昆虫を、つぶさに観察するように、内心の隅々を観察し、身についた考え方の立て直しをさせていただいた。その過程で、「自然が神です」という神の詞を知ったのである。ビンゴだ。そうか、やはりそうだったのだ・・・自然が世界を支配している。
今が何時か分からない、いつ夜が明けて日が暮れたのか分からない、サウンドステージや編集室から逃れて、ランドスケープの仕事に軸足を移すのは当然の流れだった。
妻の実父が、大学で造園学を講じていた。軽井沢の万平ホテルに長逗留して、義父から個人授業を受けた。林の道を歩き、お茶をいただき、食卓を囲みながら、「頭の中のすべてを君に話す」との言葉通りに、果てしない講義を受けた。学究の勉学はそれで充分だった。都市計画事務所が動き出した。
学校を出て最初についた「人が生きる物語の風景を作る仕事」を、スクリーンの中ではなく、現実の世の中でつかさどる。
建築士の資格はとったけれど、工学の言語だけで世界を構築する思想だけでは、みずからの仕事にならない。自然生態学に軸足をおいた都市計画、庭園都市計画と銘打って仕事を請けた。
植物生態学者宮脇昭先生が、「白井さんの仕事ならどこにでも行く」と言って下さって、森を作りながら、風景造形を模索した。
ある日、共同講演会があって、私が前座を務めた。
「私は、トラクタで畑を起こすと、その瞬間から数百年後の自然植生林復活に向けて、大地の修復が開始されるのを感じる。その力は、いったい、どこから来て、どこに向かうのか。芽吹きも収穫も、地上の出来事は、すべて、その大きな力の上で起きていることではないか。狂気や悪は、長い時間の中で淘汰されるが、同じ力の働きなのではないか・・・。人類は、その力と規範を、神と呼んできたのではないだろうか・・・」
帰りの車中で宮脇先生は、「本当だ、まったくその通りだ・・・」と、深いため息をつかれた。
生態学は科学ではないと言われることがある。生態学を科学化する努力に没頭している研究者もあるが、たどり着く先は言説、つまり、言葉である。生態学は科学的な研究を積み重ねて、思想にたどり着く。
40代は、身体の芯がいつも熱を発していた。作曲家の三枝成章さんが主催する六本木男声合唱団に籍を置いて,音楽のはなやかな世界を楽しみながら、一方で夢中に仕事に没頭し、経験の引き出しを増やしていった。理解したことは、美しい風景を作る仕事の基本は、マネジメントにある、ということだ。
スクラップ・アンド・ビルドという概念があるが、竣工した瞬間から劣化が始まるデザインと施工、金がふんだんに動くその仕事群は、死せる仕事だ。行きつく先は、ウィリアム・ギブソンが描き出すチバのように、グリスと錆のテーマパークである。
しかし、生き続ける思想の上で、代謝を続けるマネジメントこそが、人が暮らす、鮮やかな血流を感じさせる、本物の風景を作る。
設計、あるいは、都市計画家という立場は、このマネジメントを司る人々から、思想を形にする協力者としての仕事を請ける。マネジメント思想の実力が8割。私にできることは2割だ。
施主の思想を読解し、デザインの言語に置き換えて構成する。それは、施主の実力の範囲内の仕事に終始する。商業施設、住宅団地、寺院計画、イベント、日本庭園、リゾート計画・・・一通り、経験の引き出しを満たした後は、どんな仕事も不満だった。マネジメントの思想構築に参画できないからだ。知識と技術を提供するだけのコンサルタントは、生涯の仕事とは言えなかった。私は思想を練り上げたかったのだ。請負の仕事も、宮仕えも、思想的な自由はなかった。思想を紡ぐためには、自立した存在にならなければならない。伊勢の小児科医だった本居宣長は、自著出版のために、竹筒貯金をしながら言葉を紡いだ。八戸の安藤昌益もまた、町医者として自立していた。
40代なかばには、電通から依頼された第一回東京ガーデニングショー2000の総合プロデューサーを引き受け、ゴールデンウイーク全国人出トップテンを果たして成功を収めたけれど、飽き足らなかった。このままでは詰まらないと考え始めた40代後半に、神の使者が、「50歳を境に生き方を変えなさいよ」と、ぽつりとおっしゃった。そのころ縁があったのが、北海道の道東だ。考え方を変えると生き方が変わる、生き方が変わると運命が変わる・・・とは、使者の言葉だ。生き方を変えて、運命を変えて、人生の後半生にどんな果実を求めるのか。
別のある日、神の使者が、「思想家を育てたい」とぽつりとおっしゃった。そうだな、私が思索を積み重ねてきたのは思想と呼べるだろう。思想を語るためには、独立を確保する基礎を持つ必要がある。他人の思想の枠内で整理整頓を引き受ける請負仕事では、用は足りないのだ。私の自律は、何を以て経営することができるだろうか・・・
50歳を過ぎたころに、請けていた大規模な仕事が4件、立て続けに竣工した。次の仕事を請けたら、竣工は60歳に近くなる。家内と相談して、事務所を片付け、決心して二人で道東への移住を決めた。国の内外、さまざまな土地に住んだが、住民票と本籍は53年間、大船にあった。これを動かしてみよう。道東で、自然を主題にして、社会事業を興したいと、漠然と思った・・・
中国浙江省の大学に、客員研究員として席を置いたのもこのころからだ。6年間在籍して、定期的に出かけていき、大学院でランドスケープについて講義をした。そこから、臨済禅の世界に縁ができて、禅宗五山第一位だった径山萬壽禅寺の復興計画に協力し、西湖畔の霊隠寺境内にある仏教大学でも講演を繰り返した。
日本に、千年を超えて流入し続けた中国文化は、すべて径山萬壽禅寺が源流であると言われる。径山萬壽禅寺は、名山として知られる天目山の南端に位置する山岳寺院で、標高はおよそ500m。臨済禅がもっとも隆盛を誇った宋代には、3千人を超える修行僧がいたとされる。現代の近代社会がもつすべての文化文明が、宋代の中国にあった。その宋代の最高学府である。
1851年から10年間続いたとされる太平天国の乱、20世紀の日本軍侵攻、そして、文化大革命を通じて、径山萬壽禅寺は荒廃の度を極め、ついには、一面の茶畑と化していた。散逸した資料を収集しながら、宋代の偉容再現をめざす。その手助けができたのだから、それは、素晴らしい時間だった。
私はこの6年間に、「山水」を発見した。山水とは東アジア特有の自然思想だ。中国という文化の根底には、常に、この「山水」が息づいている。紀元前5世紀に、孔子は山水を語り、様々に語られた自然思想は、禅宗によって「山水」という象徴的な一言に集約されて、禅宗とともに、東アジア全域に伝播した。世界の支配者は「山水」であり、その本質と全体を一言で言い表すと「山水」であると言う思想だ。
風水は山水から派生したのだったけれど、風水学は論じられているのに、山水学がない。宗教、哲学、美術、工芸、文学、庭園、建築・・・ありとあらゆるメディアにアイコンとして登場し、思想、哲学、美意識として語られる山水を、横断して総合する学問はまだないのだ。私は、山水学創始を大学の講演で呼びかけ、それは熱狂的に迎えられ、繰り返し講演を求められた。私が今
知人がいなかったので、紹介される人に会って歩いた。何をしよう、何をすれば良いか、考え続けた。地方では、コンスタントに税金が流れ込む自治体の存在が大きい。100%民間で生きてきた身分としては、当惑することばかりだった。だまされることも多々あったが、とにかく、この地域を見極めるために、出会うものはすべて引き受けて理解を深めた。
人と人の距離がかなりあるので、誰もが個性まるだしだ。バルザックの登場人物たちみたいだと、歓声をあげながら読み解いた。ラスティニャックみたいな大悪党はいないけれど、みんな、一癖も二癖もある。
十勝海岸湖沼群は、大樹町、幕別町忠類、豊頃町にまたがるラグーン群地域だ。丘陵が海になだれ込む起伏の多い地形で、湖沼が集合する。地元に、観光に関心がないおかげで、人工物が極端に少ない。美しい。自然度が高い。これを資源化して、社会事業を興そう・・・そんなことを考えている頃、湿原生態学者辻井達一氏に出会った。
北大教授を経て、北海道環境財団理事長を15年間務めていた。気が合って、会えばいつも談論風発に花が咲いた。構想を話したら「惜しみなく協力する」と。キリスト者だった。
ラムサール条約会議座長を務めていて、様々な功績でラムサール条約賞を受賞するというので、国際会議が開催されるルーマニアに、二人で旅をした。ホフマン・ラ・ロッシュ創業一族のリュック・ホフマン氏も同席し、その後、南仏カマルグ湿原の研究所にある自宅に招かれて滞在した。1ヶ月の間、辻井達一氏の話を聞き続けた。80年の人生は、汲めど尽きぬ泉だ。
2人で一般社団法人湿原研究所を設立して、辻井氏に4年間の代表理事を依頼した。その後は私が引き受けますから、と。
しかし、設立後1年を経ずに、辻井氏は急逝した。地元の実業家に後を継いでもらい、設立後4年を経た2017年、予定通り、私が代表を引き継いだ。湖水地方自然博物館設立に向かって、2018年1月から準備委員会を開始する。
牧場を始めたのは、2013年だ。社会事業を興すといっても、地域の協力がなければならない。このような過疎地では、理屈を言っても鼻もかけてもらえない。地域の経済に参加することが絶対条件だと考えた。
十勝海岸は、夏になると海霧が陸にあがり、気温が下がる。積算温度が不足するから穀物はほとんどできない。草しかできないから酪農地帯だと人は説明した。
「海霧は資源にならないか・・・」と聞いて歩いたら、海霧が海のミネラルを運ぶから草が栄養豊富になると教えてくれる人がいた。よくよく調べていくと、大西洋に面したノルマンジーのカマンベールが同じ条件で、チーズの熟成が深く、旨みが豊かだ。海岸の草を食った羊肉は、プレサレといって高値で取引される。
熟慮の末に、海岸草原のブラウンスイス、そして、湿原の地域性を発信するために湿原のイタリア水牛、2系統酪農という、新しく、難しいビジネスモデルにたどりついた。2013年秋にやってきた5頭のブラウンスイスに触ったのが、牛に触れる初めての体験だった。だから約4年間は、地元の酪農家2代目に牧場の運営を荷ってもらった。手伝いながら、少しずつ理解して、2017年から私が細部にわたるまで牧場を支配している。乳製品製造も同様だ。地域課題解決の策として、家畜のし尿を使ったエネルギー事業も、公益事業として扱うことになるだろう。
私の今の人生は、私の経験のすべてを精査して、この随想山水記「第四巻 自然万象」に記述することにある。手掛けていることすべてが、そのためにあると言えるだろう。子供のころから、私が知っていた事実。自然が世界を支配している規範と力だと考えてきた事々。そのことが、私に、周囲とのかすかな孤立感を感じさせてきたその事実を、思想として刻印すること。
自然博物館の中に、湖水地方牧場を位置づけて、公益事業化、社会事業化を実現すること。そんな様々な仕事のすべてが、自然万象を書くためのプロローグにすぎないのだ。すでに第一楽章は書き始めた。今後、どれほどの時間を与えられるものか・・・