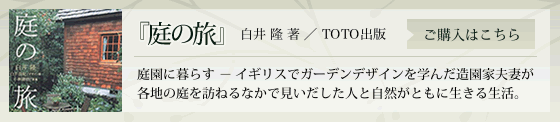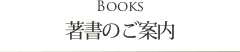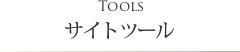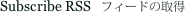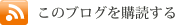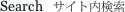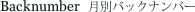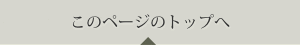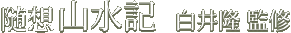柏林講座の一年 24.4.27
- 配信日
- 2017.10.01
- 記事カテゴリー:
- 第三巻 第一期湿原研究所ニュースレター・セレクション
『柏林講座の一年』
平成23年4月より、毎月第3木曜日の夜6時30分から1時間ないし1時間半ほど、環境に関する課題図書か文献を決めて、読書会の形で講座を続けて来ました。

ギャラリー陶の丹後恵さんに励まされて始めて、今では10人くらいの参加者がいますが、初めのころは会場も閑散とした雰囲気でした。この写真は23年7月23日の柏林講座で、ここに写っている丹後浩三さんと恵さんご夫妻、曽根一北海道中小企業家同友会十勝支部長が毎回のように足を運んでくださった御蔭で、なんとか一年続けることができたのです。ほかにも、河村知明さん、大石富一さん、逸見陽子さん、兼松由紀江さん、真木一博さんなどのみなさんに支えられました。ありがとうございます。この講座は、平成24年4月2日に開設した一般社団法人湿原研究所への準備として、本当に大きな力となりました。
第1回4月21日はレイチェル・カーソン「センス・オブ・ワンダー」(上遠恵子訳・新潮社)を主題としました。同時に、3月11日の東北大震災後、大樹町に住む相馬行胤氏の依頼で、福島県相双地区を訪ねた報告をしました。また、鎌倉の戸村先生から、雑誌WiLL2011年5月号に武田邦彦中部大学教授が寄稿した「原発は地震で壊れるようにできている」が、事の真相を明確に語っていると教えられたので、このテキストも一緒に読みました。
第2回5月19日は、Tim Jackson「Prosperity without growth」(earthscan)とグリーンニューディールを課題としました。「Prosperity without growth」は朝日新聞にJacksonへの取材記事が掲載されたことがきっかけで、英国から取り寄せた原書で、まだ和訳されていませんが、資本主義発祥の国英国の若い近代経済学者が、「成長」を関数とした経済学から、「環境」を関数とする経済学への転換を主張した好著で、英国で大ヒットしています。環境を関数とする限り、人間は自然環境に制約され、そして守られ、生かされるという存在と定義されるべきだということになります。霞が関では、「成長なき経済」は禁句なのだそうですが、思想的営為において最も危険なのは、自己規制です。江戸時代を作った成長なき経済は、これからも有効な選択肢の一つです。
第3回6月16日は、ヘンリー・ディヴィッド・ソローの「コッド岬」(飯田実訳/工作舎)です。アメリカ合衆国建国後まもない19世紀に、ソローは不安と希望に満ちた時代の雰囲気を良く写した思想家で、哲学者エマーソン等ともに時代を画した自然環境思想の萌芽がこの書の中に見出されます。有名な「ウォールデン-森の生活」ではなく、「コッド岬」を取り上げたのは、アメリカ第2の国立公園でもあるこのコッド岬地区は、ラグーンのある湿原地帯であり、十勝海岸湖沼群と近似する自然環境にあるからです。同時代の英国文学と米国文学の全体的な流れも概観しました。また、若き日に耽溺したソローの影響で、ウォールデンでソローが暮らした小屋を写した住宅を八ヶ岳に作り続けている造園家中谷耿一郎氏の思想の一端を知るために、白井隆著「庭の旅」(TOTO出版)から「デザインは齢をかさねた心の地図」を取り上げました。
第4回7月21日は、「生態学について」。この講座では、政府による「生物多様性基本法」を出発点にして、生物の多様性を求めるようになった生態学の誕生と、背景にある人類の歴史を概観しました。特に西洋文明における「自然観」に関して、芸術においてはルネッサンス期に初めて「自然風景」を主題に取り上げられるようになった経緯、東洋との比較。近代経済学者宇沢弘文の社会的共通資本論、司馬遼太郎の言説、北村透谷、宮澤賢治、泉鏡花、夏目漱石、志賀直哉、正岡子規、そしてルソーの「孤独な散歩者の夢想」等々、自然学を築くに至った「文体/style」という主題を取り上げました。
柏林特別講座8月6日「十勝海岸湖沼群経営の未来を考える」は、小林聡史釧路公立大学教授と矢部和夫札幌市立大学教授、藤村善安北海道大学北大植物園研究員のご厚意で実現しました。北海道中小企業家同友会環境部会のみなさんがバスで来訪され、満員の会場で、「ラムサール条約湿地について」小林聡史釧路公立大学教授、「北海道の湿原の地域性と保全」矢部和夫札幌市立大学教授、以上2講座を行いました。
第5回8月18日は、白井隆「庭の旅」(TOTO出版)。庭園の語源から始まって、中国を発祥とする自然風庭園の歴史、日本庭園史などを概観。「庭の旅」の鍵となる「庭園に暮らす」の意味を解き明かし、庭園都市計画という新しい概念を作り出した経緯を詳述しました。
第6回9月22日は、福岡正信「わら一本の革命」(春秋社)。福岡正信の評価は、西欧社会で特に高く、英国で最も入場者数の多い庭園と称される「ヘリガンの失われた庭園」においても、福岡正信の「農」の哲学はその経営思想の基礎になっています。また、オーストラリア人ビル・モリソンの「パーマカルチャー」(農文協)は、オーガニックに目覚めた若者の聖書とも称されますが、モリソンは福岡正信の弟子を自認していることは広く知られています。自然農法の世界では、その他にも優れた先達がいて、MOAの岡田茂吉、宇根豊、川口由一、木村秋則、赤峰勝人など、日本の誇りとして高く評価すべき思想家です。
第7回10月20日は、宮脇昭「いのちを守るドングリの森」(集英社新書)と、同じく宮脇昭「瓦礫を活かす『森の防波堤』が命を守る」(学研新書)。分類学から出発した近代植物学は、ドイツで発達した生態学(エコロギー)によって植物社会学に進化し、戦後世界の自然思想を塗り替えました。特にラインホルト・チュクセンは、潜在自然植生の概念を発表し、戦後ドイツの国土に森を造成する基本的なシナリオを作りました。そのチュクセンが日本の若き雑草生態学者の研究に目をつけてドイツに留学させ、後に国際生態学会長にまで成長したのが宮脇昭氏です。宮脇昭氏はチュクセンの潜在自然植生理論を日本の国土に当て嵌めて多くの論文を発表し、1972年に出版した「植物と人間」(NHK出版)では、植物生態学者の考察が世界史や文明論の構築にまで及ぶことを示して、日本の生態学潮流の先駆者となりました。その後宮脇昭氏は、潜在自然植生理論を駆使して、土地本来の森作りの手法を考案して、70年代から主に環境問題に悩む大企業の工場に深々とした森を作り続けました。その行動力は瞠目に値します。この震災後は、海岸の自然植生が津波の被害から人命を救うことを解き明かしながら、瓦礫を埋設した土塁による海岸森林帯構想を提唱し、84歳の現在も孤軍奮闘を続けています。その潜在自然植生理論と、防災林提唱の実情を課題としました。
第8回11月17日は、日本の博物学史「ケンペル・シーボルト・ツュンベリー」そして、分類学者リネンを課題としました。江戸時代の日本に博物学、つまりNatural Historyを導入したのは長崎に居住する外国人医師たちでした。当時の医師は、薬草の活用が基本ですから、卓越した植物学者です。一年に一度、オランダの領事に随伴して江戸に登る途中、街道沿いで最も自然度が高かったのは箱根山です。彼らは日本での活動に制約があったので、使用人に命じて長崎周辺の植物を採集させ、また、箱根山などで自ら採集した植物等を標本化して本国に送りました。西洋の国々による外国研究の目的は植民地経営のための情報収集ですが、その過程で日本もまた、18世紀にリンネが考案した分類学など、近代科学の基本を学習しました。
第9回12月15日は、牧野富太郎「植物記」「花物語」(ちくま学芸文庫)です。牧野富太郎は、広く知られた日本植物学の始祖と呼ぶべき学者です。経済的には決して恵まれたとは言えませんが、多くの人々に助けられながら、植物に対する深い愛情で日本の植物を体系づける重要な仕事をしました。随筆がたくさんあり、今読んでも新しい基本的な植物に対する知見が得られ、その人柄の快活さとともに、読者を若き植物学徒の気持ちに導いてくれる好著です。
第10回平成24年1月19日は、Gertrude Jekyll「ジーキルの美しい庭 花の庭の色彩設計」(土屋昌子訳/平凡社)。英語の発音は、ジークルが適当ではないかと思います。インドのニューデリー都市計画を指揮した高名な建築家エドウィン・ラッチェンスが修業時代の30歳代から40歳代前半に、60代から70歳代のジークルと組んで数百の大庭園を造ったことはあまりにも有名です。そのエドワーディアン(エドワード朝)の10年間が、英国のガーデニング発祥の時代で、女流画家からガーデンデザイナーに転身して、近代的なガーデニングの基礎を築いたのがジークルです。ラスキンの思想に影響を受け、ウィリアム・モリス等と行動を共にし、美術工芸運動の洗礼を浴びたジークルは、その初期に、自らの出身地サリー州の農民生活や道具など、その後のデザインソースとなる情報を収集して本を出版していること。その後のカラースキームによる庭園デザインの本当の意図など、このデザイナーについて語らなければならないことは山積しています。
第11回2月16日は、Beth Chatto「奇跡の庭」(清流出版)です。チャトーの庭づくりは、NHKが特集番組を作ったことで、日本でも脚光を浴びました。夫婦で移り住んだ土地が、分厚く砂利を敷き詰めた駐車場跡地や、いつも湿気が滞る湿地など、一般的には庭づくりに適さない土地だったことから、人工的に庭の用地を造成して庭園を造るのではく、その土地の条件に合わせて、「砂利地の庭」、「湿地の庭」、「日陰の庭」、「乾地の庭」など、その条件が持っている生態学に応じて庭園を構成するという考え方を生み出しました。この考え方から、十勝海岸湖沼群の自然庭園論まではあと一歩。チャトーの庭園を囲む境界線を消してしまえば良いのです。
第12回3月15日は、「辻井達一を読む――『湿地』(中公新書)」。湿地湿原論の基礎をここで学びました。4月2日に、十勝海岸湖沼群経営を目的とする一般社団法人湿原研究所を設立することが決まり、その代表理事に招聘する辻井達一氏の本と論文を読むシリーズ「辻井達一を読む」を、この月から始めて計5回、7月まで続けます。4月の「辻井達一を読む」は、「湿地と生物多様性」、5月は「湿原と農業」、6月は「湿原と植物」、7月は「湿原と観光」を予定しています。また、7月には辻井達一氏がルーマニアで開催されるラムサール会議においてラムサール賞を受賞することが決まったことを受けて、8月の晩成学舎特別講座において、辻井達一氏に講演を依頼しました。
柏林講座で語り合った事象は、多かれ少なかれ、今後の一般社団法人湿原研究所の活動に反映するものと考えられます。このニュースレター#10では全体の流れの紹介にとどめますが、今後、平成24年度の柏林講座等のニュースレターはもちろん、平成23年度柏林講座の各一回分ごとの概説を、ニュースレターとしてまとめて発信することで、参加される会員の方々への道程とすることにします。