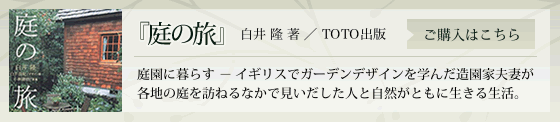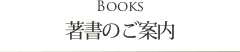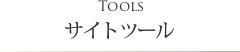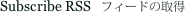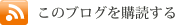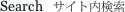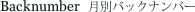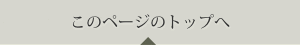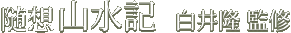自然栽培 24.4.23
- 配信日
- 2017.10.01
- 記事カテゴリー:
- 第三巻 第一期湿原研究所ニュースレター・セレクション
帯広市愛国の自然栽培農家「やぶたファーム」を訪問しました。
「自然栽培」をどう考えるか・・・・。自然栽培とは一般に、無肥料無農薬栽培を意味します。もちろん除草剤の使用は論外です。
雑草で思い出すのが、若き日に雑草生態学を志した植物生態学者宮脇昭氏の、「いのちを守るドングリの森」(集英社新書)に書かれたこの一節です。
「雑草はほとんどが外来種である。路傍、人家のまわりの空き地などで一般的に見られるのは、オオアレチノギク、ヒメムカシヨモギなど明治以降に北アメリカから入ったといわれているキク科の帰化植物である。耕作畑地の雑草は302種類あるが、ネザサを除いてすべて外国からの侵入植物である。また水田雑草は、92種類中ウリカワとコナギを除いては、東南アジアをはじめ、ほとんどが世界各地から入ってきた帰化植物である。コスモポリタンといわれている。」
植物生態学によれば、植物は立地環境に適合した様々な社会(群集)を形成しており、時には数百種類にもなる植物と、昆虫、土壌微生物などが互いに牽制しあい、少し競争し少し頼りあって生存している。特にその自然植生が安定的な状態にある時には、堅固に排他的な植物社会を形成しているため、外来種は入り込むことができない。したがって、外来種は、人為的にあるいは自然災害などで自然植生が攪乱された場合に、その裸地に飛び込む。それを私たちは雑草と呼んでいる訳です。
前述の宮脇昭氏は、子供の頃に農業を営んでいた両親が雑草駆除に追いまくられる姿を見ていたので、農薬には頼らずになんとかとして簡単に雑草を駆除する方法を見出したいという一心から雑草生態学を志したそうです。そして、雑草を生やさないためには、「耕さないこと」に尽きると語っています。つまり、支配しようとしないこと、自然の力に頼ること。人間の参加の仕方を変えろということでしょうか。
自然栽培、自然農法を考える時、この生態学が出発点になります。
やぶたファームを含む自然栽培の仕事は、新聞などで紹介されることがあるのでご存知の方もあるかもしれません。自然栽培が提起している究極の農業も、「耕さない農業」=不耕起栽培です。

このビニルハウスは、2006年から耕すことをやめました。土の上に枯葉を50ミリから100ミリていど敷いてあり、種を播くときにそれをどかして播きます。今はホウレンソウが芽を吹いています。ホウレンソウの収穫を終えたら、今ホウレンソウが伸びているところに枯葉を移してそこを通路にし、今枯葉のあるところに種を播くのだそうです。
もちろん、生態学者の言う自然植生がこの畑で実現している訳ではありません。しかしこの畑で、肥料も、ほとんど水もやらずに、作物は育つ。もちろん農薬は使用しません。
「奇跡のリンゴ」で知られた木村秋則氏は、このように語っています。
「豆科の作物は地中に根粒菌を作って大気中の窒素を固定し、植物に供給するが、地中に窒素が足りてくると根粒菌はできなくなる。有機であろうと、無機であろうと、肥料を大量に投与しても、豆科の植物は根粒菌を作る。植物は、人が与える窒素を、植物が必要としている窒素とはみなしていないのではないか」
植物が必要としている養分は、土中の微生物が植物と協力しあって作り出していると言うのです。

上記の写真の畑は、高畝を作ってありますが、これも耕さずに枯草をどかして播種します。それで、麦でも、豆でも、作ります。やぶたファームは、少量多品種と称される農業ですから、不耕起、無肥料、無農薬で、それこそ何でも作ります。北海道にはこのような自然栽培の農家が多く、滋味の格別に豊かな素晴らしい作物を生産しています。
農業生産法人株式会社大樹農社も過去二年間、自然栽培で蕎麦を作りました。蕎麦というと全部自然栽培ではないかと思っている人が多くみられますが、北海道で大規模栽培される蕎麦の大半は、除草剤などの大量投与に支えられています。一般社団法人湿原研究所では、これら自然栽培作物の加工および流通の研究を始めました。幕別の森農園、北海道有機農業協同組合の作物など、首都圏からの距離による流通経費を含めて、様々な課題を克服することが必要です。特に消費者に対する情報の提供は鍵でしょう。この件は改めて機会を作って報告しなければならないと思います。
さて、TPPを通して農業を語る人は、「農業が衰退すると、十勝の農地はどんどん藪になり、ついには森に覆われてしまう。先祖が苦労して開墾した農地は、元の木阿弥だ」と言うのです。農地を放棄すれば将来は森に還る、それは事実です。農地は放置すると、初年度は外来種の植物がはびこりますが、翌年にはヨモギやタデなどの在来植物群が支配し始め、数年のうちには先駆植物=パイオニアと呼ばれる樹木が生えて樹冠が土地を被います。
北海道ではシラカバが先駆植物の代表選手として知られています。そして、数百年の時間の流れの中で、自然植生に向かう。それが何を意味するかと言えば、地球は人間によって攪乱されても、常にその瞬間から原植生に向かって活動を始めているということです。元植生を駆逐して長い年月が経過すると、地下水位の低下、気候の変動等により、植物にとって基本となる条件が変化するため、元植生には戻れなくなるが、現在の条件に合った自然植生に向かう。それをドイツ人植物学者ラインホルト・チュクセン(Reinhold Tuexen)は「潜在自然植生」と呼び、戦後のドイツにおける森の復興計画の基本的シナリオとしたのです。
自然が持っている力とその原理は、この世の「道理」です。私たちがどんなに自然破壊を行っても、その瞬間から自然は常に、「自然状態」の回復に向かって動き始める。長い目で見れば、地上に悪は栄えないように、道理の力が働く。
畑も同様です。自然栽培の畑は、その自然の力に大いに頼る農法だと言えます。人間が畑を支配して、力づくで思うが儘に作物を作らせようとするのではなく、自然の支配力を理解し、目を凝らし、耳を澄ませ、深く感じ、その力に合わせて人もまた自然の律動に寄り添うように作物の種を播くと、自然の力はそれに応えてくれる。狩猟生活から農耕を覚えた人間が、今後、自然栽培の方法と哲学的思索を獲得することは、人間の進化の過程ではないかと思えるのです。
自然状態とは、高山帯や南極北極、沙漠、海岸、湿地などのような条件の場所以外は、自然植生の森を意味します。この道理の力が働いている限りは、関東地方だって、人間が地上から消えて300年も経過すればシラカシの森に還ると考えられています。しかし問題は、私達の生存を保証する自然環境を徹底的に破壊してしまえば、私達は生き延びることができない、という点です。
私達が国民総生産と称して大切にする富を生み出す原動力は、「近代」という思想の所産ですが、その近代を世界で最も旺盛に謳歌する西洋民族とその文化を生み出した人々の歴史は、ギリシャ、ローマ、エジプト、メソポタミアを見ても分かりますが、森の中に文化文明を生み出し、森を駆逐し尽くして衰亡し、森のある土地に移動してまた森を消費しながら発展してきました。
ドイツをはじめとする欧州各国は、近年猛烈に反省をして、民族哲学の再構築を試みていますが、その鬼子はアメリカです。彼らは、東海岸から西に向かって森を消費しつつ開発し尽くし、さらに新たなフロンティアを求めて、太平洋を超えて極東から収奪を続けています。新聞が語るアメリカの世界戦略とはこのことを意味しているのです。知己を得たアメリカ政府官僚が、日本を「最後のフロンティア」と呼んでいたのが、とても印象的です。東アジア征服戦略・・・安政の開国以来、日本を含む東アジアが直面している現実がこれです。
第二次世界大戦の勝利で飛躍的な足掛かりを得て、日本、韓国の征服に成功し、TPPはその仕上げと言われていますが、中南米や中東でアメリカがやってきた近現代史を振り返れば、TPPの次は戦争をさせるでしょう。戦争は即効性のある「おいしい商売」だからです。
世界は「道理」によって支配されているのですから、長い長い目で見れば、それは恐るるに足りぬことなのかも知れません。癌細胞のように破壊を尽くした後、食い散らかす餌がなくなれば、その癌細胞もまた死滅するのです。その後の廃墟にも道理の力は働いて、地球の修復は瞬時にして始まるでしょう。しかし、その破壊力によって民族の寄って立つものを失うか、あるいは、東アジアにおいて日本を含むいくつかの民族が消滅することは大いに考えられることです。
生態学では、植物生態学と人間の生態学は同一であると語ります。つまり、アナロジーではなく、ホモロジーだと言うのです。生態学の観点から見て、西洋の歴史から学ばなければならない重要な点は、その歴史上に見られた森の破壊は壊滅的で、ギリシャ、ローマ、エジプト、メソポタミアなどがすでに沙漠化して、回復不可能にすら見えるという点です。
道理はとてつもなく長い時間を費やして、いつかはその沙漠を自然植生の森に還すだろうと思われますが、それは人間の尺度を越えた絶望的に長い時間を必要とすると思われます。今の日本を森に見立てれば、それは破壊し尽くされて沙漠化する道程にあるのです。
畑の自然栽培について考えながら、私達は果たして、壊滅的な破壊という衝動から自由になることは可能なのだろうかと自問します。
近代農業の技術の枠組みを少し修正する、たとえば農薬の使用量を半分に減らすなどの部分的変更で未来は拓けるのか。
根源的な思想の転換は必要ないだろうか。
自然征服に対する信仰は、自然とのより高度な関係構築への意志によって置き替えられるべきではないのか。
私達は自然の道理の力との均衡を手に入れることができるのか。
どんな思想を構築したら、破壊的な外来種の攻撃を跳ね返すことができるほどの社会を構築できるのか。
道理を味方にすることで、生き延びる道を歩むことはできないか。
力強い自然社会というものを、ホモロジーで日本民族に置き替えた場合、私達が人間生態学的に必要とする人間社会とは、どんな内容なのか。
一般社団法人湿原研究所の辻井達一代表理事は、植物生態学と人間社会学をホモロジーであると語る以上に、植物も動物も人間も地質学もなにもかも含む、この世全体を語る視点と言葉を探して来た生態学者です。全体を語る生態学が湿原に特化して来たということは象徴的な出来事で、湿地湿原は命が生まれる場、形成に失敗した社会を一度混沌に戻すことができる場だからであろうと思われます。日本は一度、「豊葦原千五百秋瑞穂国」(とよあしはらのちいおあきのみずほのくに)に立ち返って、自らの国の本質を問いなおすことはできないのでしょうか。
自然は、一見とてもか弱い存在です。人柄に置き替えれば、とても優しく穏やかで、謙虚で鷹揚です。私たちが語る「自然な人柄」とは、そのような立居振る舞いを指しているのですが、そこに真実が隠されているという知恵を、私達は思い出したいものです。
自然の背後に隠れている道理は厳しいもので、確かにこの世を支配しているが、富や力を誇示するようなチンピラの心の中にではなく、一見弱々しく優しい自然な人柄の中にこそ、道理の発露としての賢者の知恵がある。日本民族は、心の深層にその記憶を持っているはずだからです。
一般社団法人湿原研究所は、海岸湖沼群の経営=自然環境経営を主題としています。重機でなぎ倒してしまえば一瞬にして姿を消してしまうような自然の中に、人が頭を垂れなければならない道理が隠されている。だから私たちは限りなく謙虚になって、この事実から多くを学び、来るべき人間の思想の構築とその実践に向かいたいと思います。 24.4.23