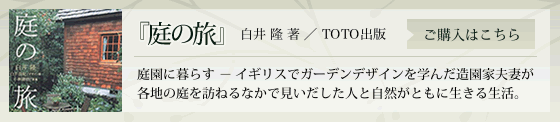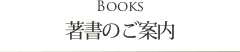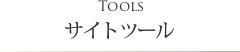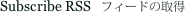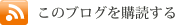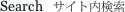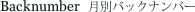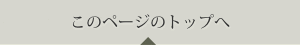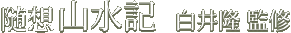研究ノート『湿原生態学者 辻井達一との対話』
- 配信日
- 2018.03.21
- 記事カテゴリー:
- 第二巻 湖水地方自然博物館
以下は、2013年1月に急逝された辻井達一氏の追悼文として、湿地学会誌から求められて書いた。辻井達一氏は、北海道の自然世界に私を誘導してくださった。
氏は、2012年7月に、ルーマニアのブカレストで開催されたラムサール条約国際会議において、ラムサール科学賞を授与された。その旅に誘われ、一か月のあいだ、二人でルーマニアから南仏まで旅をした。その際に、上機嫌で話し続ける辻井氏の饒舌を毎日のようにコンピュータに打ち込んだ。
この原稿は、その記録を対話集として紡いだものである。
研究ノート『湿原生態学者 辻井達一氏との対話』
知り合いの国交省OBが、北海道開発局時代に知っていた辻井達一先生を紹介してくれた。辻井達一先生は、初めて会った私に気さくに語りかけて、アハハアハハと大笑いしながら談論風発を楽しんだ。件の国交省のOBは、札幌駅に向って歩きながら、
「楽しんで話すのは結構だが、あの人は、煙草屋のオヤジではない、並みの人物ではないんだ」
と、詰まらなそうに言った。
煙草屋のオヤジではないだろうが、無暗に威張る人物ではないなと、私は思った。
東北大震災があった年に、札幌で生態学会があった。
「総合的に語らなければならない。自然科学の学者だけでは、生態学にならない。風景とか、建築とか、そういうことに携わってきた人にも参加してもらいたいから、来られないか」ということを、辻井達一先生から持ちかけられて、喜んで参加した。
「若手の学者が来るから、気に入った奴を仲間に引き入れて、白井さんがやりたいことをやればいい」
と辻井達一先生は言った。その日、すてきなマントを羽織り、
「先に帰るよ」
と言ったが、
「君は懇親会で、皆と交流したが良い」
と言った。
札幌市立大学の矢部和夫教授に、
「僕は、自然環境の研究所を作ろうと思って北海道に来たが、ラグーンと湿原の地域で、だから湿原研究所ということになるのだと思う」
と告白したら、
「辻井達一先生に相談しろ」
と言った。何かと反論してみたが、
「何でもいいから、辻井達一先生だ」
と主張するので、後日、改めて辻井達一先生を訪ねて、
「湿原研究所を作りたい」
と申しあげた。すると、
「惜しみなく協力しますよ」と言った。キリスト者みたいなことを言う人だなと思った。
白井隆庭園都市計画事務所の仕事にご協力いただいている生態学者・宮脇昭博士にそのことを伝えると、
「辻井君とは昔湿原の研究で一緒になったことがある。しっかりした奥様にもお会いした。辻井君は不思議な人だ。年齢を重ねるにつれて、ますます活躍の場を広げている。それにしても、君は湿原に限定することはないじゃないか。生態学は地球全体が研究対象だ」
と言う。しばらく考えたが、後日、
「やはり、辻井達一先生に世話になるのだから、湿原研究所で行く」
と申し上げると、
「そうか、それならそれでいい」
と言った。
実は、私は、湿原生態学という分野があることを知らず、辻井達一先生が湿原生態学の先駆者だとは知らなかった。わざわざ湿原生態学を名乗る必要も理解していなかった。2011年には大樹町の我が家を訪ねて下さって、妻の手料理で夕食を囲んだ。
「辻井先生は植物学者ですか」
と尋ねたら、
「湿原が研究対象です」
とおっしゃった。淡泊な関係だった。それで良かったのだ。
2012年の4月に研究所作ることを決めた。
辻井達一先生を知る人々からは、
「辻井先生の弟子がやるべきことをやってくれる」
と感謝された。それで、2011年の4月から、町の生涯学習会館研修室を借りて、月に一度、『柏林講座』と題した読書会を始め、湿原やラムサール条約の資料を読み、2012年の3月からは、『辻井達一を読む』と題して、これまでの著書や論文を題材にした。7月まで続けたから、計5回続けた。辻井達一先生からは、「光栄です」とハガキをいただいたが、私は、辻井達一先生が何をしてきたのかを知っておくべきだと考えたのだ。
2012年の4月に発足した一般社団法人湿原研究所の代表理事に、辻井達一先生に立っていただいた。ラーサール国際会議でラムサール賞を受賞する事が決まった際に、
「私がラムサール会議に出席するのは、これが最後にしようと思うから、一緒に行きませんか」
と、口説き文句を言った。誘われたのは嬉しかった。ありがたい話なのに実に済まなそうに言うので、軽い反発心が動いて、その場で「行きますよ」と答えた。そういう、人の心のやり取りを引き出すのが実に上手で、本人もそれを楽しんでおられた。落語にある江戸の下町の人情話みたいに、物語を作って動かして嬉しそうだった。私も分かってはいたが、先達の言うことはすべて受け入れてみるということを、自分に言い聞かせていたから、辻井達一先生が言うことは、まず断らずにすべて着手することにした。私が、あまり素直に何でも受け入れるので、たぶん、途中で心配になったらしい。こちらも、その心配顔を楽しんだ。それも、辻井達一先生は分かっていた。まあ、そういう人だった。
でも、おだてられて木に登った人は幸運だったと思う。平凡で退屈だった人生に目標を与えられて、必死に歩き続ける人生に変わるからだ。ブカレストのラムサール条約会議の後、ド・ゴール空港から南仏に向かうTGVの中で、
「3年後のウルグアイのラムサール条約会議にも出たくなった。行ってもいいかな」
と言っていたから、計算づくの口説き文句だった。いや、ルーマニアに出掛ける前には、半分は本気で最後だと思ったのかも知れない。最後というのは難しい。命の最後を迎える時にも、人は、半分くらいは作り話だとしか思えないに違いない。目を閉じて眠って、再び夜が空けたら、また同じ朝が来るに違いない、と。
19世紀初頭に、若き文学者エッカーマンが書いた『ゲーテとの対話』は、10年間にわたる師ゲーテとの毎夜の語らいを記録した実に優れた書である。自らの文化の出自を確認する作業として、これほど質の高い仕事を他に知らない。会社員は創業者あるいは経営者の、生徒は教師の、子は父の、思想あるいは人となりを知ることが、自らの背景を認識するためにどれほど重要な営為であるか。皆、聞き書きをして書き記してみたらどうだろう。生物社会は宿命的に縦社会なのであってみれば、人生の重要な舵取りを託す人物の思想を知るべきだろう。感情的な反発や幼稚な不満などよりも、理知的な理解を優先させ、先人を越えて、少しずつでも人として進化する楽しみを覚えることが可能になるはずなのだから。
ラムサール会議に関して、私には高校生ほどの知識もなかったが、ラムサール賞授賞式で、ラムサール賞というものを受賞する辻井達一先生を眺めながら、「私が知らない世界がここにはあるのだ」と理解した。それで、せっかく4週間も同行する良い機会だから、『ラムサール会議報告』とは別に、辻井達一先生が話す内容をなるべく詳細に書き記してみようと思った。湿原研究所の礎に、81年の時間をいただかなければ勿体無い。それに、人の叡智、その人となりというものは、案外、力強い弁舌よりも、何気ないつぶやきの中に立ち現れるものである。書き記した文章の細部に、読むに値する「言葉」が見出されるように、努力した。
7月3日、ド・ゴール空港で待ち合わせて、おなじ飛行機でブカレストに着いた。夜11時を過ぎてホテルに到着してから、ホテルのバーに座って話した・・・
***************************************
ギリシャのパパヤニスThymio Papayannisという人物は、欧州の湿地委員会/MedWetの委員長をしていて、このラムサール会議では欧州の代表という立場にある。「湿地の文化と技術」と言うと、なんでも大きい方が優れていると考えるらしい。例えば、欧州の湿地技術と言うと、イタリアの水道橋の技術を持ち出したりする。湿原の技術とは壮大なものだと言うのだ。
ギリシャのThymio Papayanisと
一方のアジアでは、田植えの祭や、タイの水かけ祭り、ベトナムの水上人形劇、どれも収穫の祭で、いわば無形文化財のようなものを持ち出してくる。
中近東では、地面の中にトンネルを掘った水路などと言う。
だから簡単に言えば、欧州では水の灌漑を湿原の技術と言い、アジアでは、技術と言えば排水の技術だ。アジアモンスーンだから。もっとも北海道は降水量が少ないが。
モンゴルはテキサスみたいな土地で、植生が乏しいからか、耕作を悪と思っているようだ。乏しい地表の草を耕作でひっくり返すことを良しとしないらしい。
草炭研究会という会があって、草炭とは泥炭のことを意味するのだが、北海道の泥炭を中国の沙漠の緑化に使うというから、私は大反対したことがある。だって、泥炭は幾ら水持ちが良いからといっても、沙漠に持っていけば乾燥して分解するだけだ。無駄だからやめろと言った。今はやめたらしいが。沙漠の緑化というのは、いきなり樹木を植えるのではなくて、草から始めたら良いのではないか。順を追って、次に潅木、そして高木という具合に。沙漠は地下水位も低くなっているし。順を追って。
森林ができれば冬は雪が溜まる。針葉樹の場合、林床に雪が積もって雪解けが遅くなるから。晩春までもてば、その時期に雨が降る。
十勝には昔カシワやミズナラの大木が生い茂っていた。依田勉三は、十勝は昼なお暗き森林であると言った。ほんの100年かもう少し前には、まだ大木がたくさんあった。しかしみんな切った。カシワはタンニンを取って稼いだし、ミズナラは枕木として良いから切った。とにかく薪として火が長くもつから、切って使った。今ではみんなひょろひょろの木だ。少し我慢して、100年くらいは我慢して、大木にしてから切るようにできないものか。
阿寒の前田一歩園では、ミズナラの苗木を植えている。私も理事の一人。ミズナラも150年から200年たつと、実に良い材が取れる。大きな一枚の板でテーブルを作れば、100万円単位で売れる。テーブルにしてから年月が経てばさらに高く売れる。ミズナラは欧州では高級家具材だ。北海道人は刹那的で、どうしても目先の金ばかり追いかける。
黒松内は、ブナの北限で、ブナを売り出そうとしている。私も学生時代に教授について歩いたが、ドイツの学者を招いたら、
「日本にはどうして曲がりくねったブナばかりあるのか」
と不思議そうに見ていた。確かに、ドイツのリューネブルガーなどで見るブナは真っ直ぐに空に伸びている。ドイツ人はブナを大切にするよ。あとはカシワだ。スギやヒノキがドイツにはないからね。
ブナは乾燥すると暴れて捩れるから、ドイツではそれを矯正する技術が進んだ。最近では日本にもその技術が定着しているけれど。戦後は日本でブナのインチ材をたくさん欧州に売った。日本人はスギやヒノキの、年輪が真っ直ぐな材が好きだからね。表面にぶつぶつ斑点みたいな模様が出るブナは嫌われた。
デンマークの有名な家具デザイナーは、ブナで家具を作って、その昔1脚20万円くらいした。その当時、日本では、ブナ材でリンゴ箱を作った。1箱200円だった。もう少し、世界の事情も知って材の扱いをすれば、良い仕事と収入につながるのにと残念だった。職人を大切にしなければ。
音威子府に美術工芸高校がある。元は村立高校で、今は町立だが、美術工芸高校なんて、大した見識だと思う。
美術工芸運動という、英国の19世末に起きた運動に影響されているのだろうな。
それにしても、村立で美術工芸高校を持つというのは、たいしたことだよ。
もともと森林が豊かな土地だが、その高校にはすごい旋盤があったり、寄宿舎も完備している。生徒は減ってくる。だから、社会人教育を受け入れて、それこそ、退職組だって受け入れたら良いじゃないかと言った。本当は職人になりたかったのに、仕方なく銀行員になったなんて人は幾らもいるのだから。彼らが誇りを持って、改めて学習する場を作ったらどうだと言ったんだ。社会人なら、色々なものを見てきている。就職の世話に追われることもない。
標茶高校は元々農業高校だった。やめろと言ったが、普通高校に変えてしまった。それでもソーセージやハムを作る工房はあるから、生徒が作ってそれを町に売っている。酪農の設備もある。湿原研究もしていて縁があるのだが。根釧台地だから。寄宿舎も完備している。だからこれから国際高校にしてロシアや中国東北部の生徒も受け入れたらどうだと言っている。奨学金もつけて、受け入れる。将来、彼らとの関係が役に立つだろう。でもやらない。だから予定通りに生徒数が減ってきた。勿体ない。農地だって200haから300haも持っている。湿原研究所と共同研究や共同事業ができたら良いね。こつこつ交渉すれば、道は開けるのではないか。
教育委員会は硬いからね。カチカチで面白くない。前例のないことはしない。以前大学にいた頃、文化財の委員会の委員をやった。研究室から自転車で行けるところにあったから、ある日、委員会に行こうとして自転車に乗ったが、途中で嫌になって帰ってきたことがある。秘書が「登校拒否だ」と触れて回って笑われたが。結論が決まっている委員会なんて、出たってしようがない。嫌で嫌で・・・。
帯広市の給食がまずいと評判? あれも、教育委員会だから、手が出せない。栄養士は決まりきった計算をするだけだ。今日油っこいものが出ても、明日さっぱりすれば良いじゃないか、どこかで帳尻が合うように柔軟に考えれば良いのに、なんでも杓子定規だからな。
ラムサール会議事務局が主催した、ラムサール賞受賞者を囲む夕食会で。左から辻井達一氏、アメリカのThe Wisconsin Wetlands Association代表、ギニアビサウのAugusta Henriques、ラムサール会議、WWFなどの創立者Luc Hoffmann、ギリシャのThymio Papayannis。私は、辻井達一先生のご配慮でこの夕食会に参列させていただき、得難い経験と、機会と、知己を得た。過分な配慮に対して礼を述べた時、辻井達一先生は少し嬉しそうに微笑んだが、何も言わなかった。恩に着ることばかりで、恩に着せることのない人だった。
雑誌『モーリー』の編集委員長をしているけれど、最近雑誌のサイズを変えたから、中身を変えようと言って、北海道を見直す企画を一年やることにした。一年といっても、季刊だから4冊。「熊の言い分、鹿の取り分」という企画で、今、各界の関係者に書いてもらっている。殺すなとか、増えすぎたとか、目先のことばかり言うけれど。
昔、苫小牧の近くに鹿肉の缶詰工場ができた。一年に8000頭ずつ獲ったが、3年ももたなかった。急激に鹿の頭数が減ったから。動物は自然界では増えすぎると減る、栄養学的に問題が起きるなどの原因があるのだろう。今の鹿対策は、場当たりではないか。儲かるのはフェンス会社ばかりだ。全部の畑に鹿用柵を作るわけにはいかない。その場しのぎではダメだろう。
生物多様性会議というのが名古屋であった。COP10だ。私もWIJの人間として参加したが、生物多様性という言葉は誤解を生むと思った。不同性という言葉はどうかなと。DIVERSITYという語には、種類の数が多けりゃ良いという意味は含まれていないし。ともすれば、考えかたの自由勝手気ままと取り違える人もいる。生物は人間も含めて、分をわきまえて生きているからね。決して勝手気ままではない。
インドにチリカ湖がある。ラムサール条約登録湿地だ。チリカラグーンオーソリティ、私たちはチリカ開発公社と呼んでいる公社があって、副総裁がパトナイク。チリカ湖の水質劣化を調査しに行ったことがある。サロマ湖に似ているが、面積はサロマ湖の10倍くらい。琵琶湖の1.5倍。大きな湖だ。水質劣化の原因は、ラグーンだから砂州で海への出口が閉ざされている。それで色々な汚物が溜まる。サロマ湖の話を聞かせた。最も貧しかった漁協が、今では金持ちの漁協になった話だ。パトナイクは、サロマ湖を見に来たいが、金がない。それで日本に帰って、なんとかして金をかき集めて、パトナイクをはじめとして何人か来た。サロマ湖の砂州を切って水を入れ替えるのを見せた。
パトナイクは帰ってからさっそく工事を開始した。二年かかって工事完了したら、劇的に状況が好転した。3ヶ月間で漁獲量は1.4倍に増えた。漁民は14万人いたが、全員の収入が1.4倍に増えた計算になる。パトナイクは喜んだ。後にビジターセンターを作る際に、サロマ湖に対する感謝の意味で、入口に帆立貝のレリーフを飾った。私の今回のラムサール賞受賞も、パトナイクの強力な推薦があった。
このように、アジアだけでなくとも、他の国をそのように手伝うというのは、本当に魅力的な仕事だ。今の日本なら、人を助けるささやかな金と、豊富な知恵と技術がある。
残念ながら、サロマ湖はラムサール条約には登録していない。サロマ湖漁協はチリカ湖との交流もあるし、ラムサール会議で世界中の関係者と交流をしたらどんなに素敵だろうかと思う。でも、サロマ湖を囲む漁協のうち、二つの漁協のトツプが反対している。
それはね、環境省がサロマ湖に説明に行くと言った時に、私も行きましょうか、と言ったのだが、若い担当官が自分で行くからいらないと言う。心配したが案の定、現地の漁業関係者から多くの質問が出ても、まともな受け答えができなかった。それで不信感を持たれた。人を説得するというのは、重要な仕事だ。サロマ湖の経営はうまくいっているが、文化として育てる、世界と交流するというのは実現できていない。実に残念だ。
十勝の湖水地方経営は、ぜひとも最良の道をたどって欲しい。私は、十勝海岸湖沼群はとても手がつかないと考えていた。なにしろ自然調査のデータがない。地元に人材がいない。町が複数にまたがっていて調整が難しい。そんなふうに考えていた。
ブカレストの街角で
大雪を世界遺産に登録しようと考えて動いたが、やはりうまくいかない。7つの町村があって、全部思惑が違う。興味がまったくない町、あそこが参加するならうちは参加しないという町、色々あって・・・ それに、地主は林野庁で、環境省はそんな面倒なことには手を出さない。
知床は斜里町と羅臼町をうまくまとめることができたが。
地元の人にとって、何が誇らしいものになるか。世界に誇れるものを持つ。北海道湖水地方は、やはり生物多様性だろう。その点で日本は世界で群を抜いている。その日本でも、湖水地方は群を抜いているだろう。プライドをもって対処する。
まず、植物、動物、底生生物などなど、種類が抜群に多い。リストを作ってみる。一度に全部はできないから、やはり専門家を入れて、最新の情報も取る。
ラムサール条約に登録しなくても良いではないか、地域の経営が成り立てば良いのだろうと考えるのはわかる。でも、登録すれば、国内の他のラムサール湿地との交流も、世界中の友人とも交流ができる。こんな世界会議に地元の活動を発表したり、助け合ったりできる。課題解決のために、世界中から協力者を募ることができる・・・その力は計り知れないだろう。
会議は、幾つかの基準がある。この条件を一つでも満たせば、申請できる。どの基準に絞るか、作戦を立てる必要がある。
北大に、観光高等研究院という大学院があって、社会人なども盛んに参加して、観光学をやっている。石森という人物が院長。ここと連携して、来たるべき北海道の観光の姿を追い求めてはどうだろうか。
加賀市長は元観光協会にいた。彼を呼んで、マガモを捕まえる鳥獣保護区について、解説をしてもらってはどうか。
湖水地方の鳥獣保護区を拡大しようと北海道が準備しているが、地元は大反対?地元で十分な議論をして意見をもとめ、湖水地方ならではの補則の制定を提案してはどうか。だいたい、鳥獣保護というのは元々狩猟を趣味とするハンター連中が始めたことだ。連中は、鳥の数が壊滅的に減ったら困る。だから、種を保存するために必要な絶対数を守る。余分な数を狩猟の対象にした。
ラムサール会議は、多国間の条約会議なので、民間の会議みたいに学者が出てきて研究を発表するというのとは少し違う。なんだ、お前は理屈ばかりで、現場で何もしてないじゃないか、みたいな人もいる。インドのパトナイクなんてのは、実際に現場で活動してきた人物だ。明日きっと会えるよ・・・・・
***********************************
7月6日、辻井達一先生は、ルーマニアの首都ブカレストで開催された第11回ラムサール会議において、ラーサール賞を受賞した。
午後行われた記者会見にて。ラムサール賞を受賞した5人。左から、The Wisconsin Wetlands Association (米国)の代表、辻井達一一般社団法人湿原研究所代表理事、Augusta Henriques(Guinea-Biseau)、Thymio Papayannis(Greece)、Dr. Luc Hoffmann。
この5人が、どんな人々であるのかを簡単に解説することで、ラムサール会議というものの性格の一端を伝えられるのではないかと思われるので紹介しよう。
ラムサール賞には、教育、経営、科学の3部門がある。
教育部門は、かつて中村玲子さんが受賞なさった賞だ。この年の会議では、The Wisconsin Wetlands Associationに与えられた。米国の湿原教育、湿原保全参加、湿原意識の向上、そして、ラムサール条約に対する理解を高めるという点で、米国で主導的な活動を果たした団体。1969年に設立された、米国で最も古い湿原保全NGO団体で、科学研究に基づく企画、教育、啓発活動を通して、ウィスコンシン州の湿原保全と教育活動に努力を傾注してきた。
科学は、辻井達一先生。国の内外で、科学者としての知見を以て、湿原の科学と保全に献身的な活動を続けてきた。日本での湿原保全の主導的な地位にあり、特に有名な釧路湿原をラムサール条約登録湿地、世界遺産に育てるのに尽力した。日本のラムサール登録湿地の全てに関わり、政治と民間の両方において、日本における湿地に対する意識を高めるという決定的な仕事をした。
ラムサール事務局長は、日本をラムサール会議のチャンピオンと評する。国会に、「ラムサール国会議員連盟」があるのは、世界で日本だけだと言うのだ。今や、世界で最も湿地文化の評価が進んだ国と認められているが、辻井達一先生の努力の成果であることを、世界中が顕彰した受賞式であった。
辻井先生は、カッパという民話の生き物をみずからに喩えて、辻井氏の人柄を知る満場の参加者から盛大な拍手で迎えられた。
経営は、Augusta Henriques(Guinea-Biseau)。1991年に設立されたNGO団体Tiniguena(「この土地は我らのもの」)で献身的な役割を果たし、マングローヴ林、マナティ、ウミガメなど生物相の豊かなBijagos ArchipelagoにあるUrok Islandsで、Community Marine Protected Areaの創造に指導的な役割を果たした。彼女はその土地の文化を育て、自然保護を進めるために、ラムサール会議の理念を存分に活用した。彼女は、各世代を巻き込み、特にarchipelagoの全村に対話を促進したことが、成功への道を開いた。自然資源活用の主導権を地元民の手に取り戻し、政府を動かし、地域内の小さな事業間に交流を促し、資金は国際的な団体から調達した。Guinea-Biseau政府、そしてWWF、Wetlands International、IUCN、FIBAなど国際的な団体とも連携して、西アフリカにおける自然環境経営に重要な成果をあげた。
教育、科学、経営の3部門以外にも、2人の受賞者がいた。
ラムサール貢献賞は、Thymio Papayannis(Greece)。ギリシャ、地中海地方、そして世界で、Wetlandsの保全と活用と文化に優れた指導力を発揮し、ラムサール会議では25年の活動を続けてきた。Luc Hoffmann氏と共同で、ギリシャと地中海地域に多くの環境団体、研究機関を設立した。特にMedwetの立ち上げに10年間の決定的な仕事を果たし、今も相談役として貢献している。彼の仕事と著作は、Wetlandsの価値を人々に教え、特にWetlandsの文化的価値を会議に紹介したことは独自の仕事となった。「Wetlandsが潜在的に持つ資源を活用することは、人間の知性の進化に結びつく。人間とWetlandsの関係を構築するという概念は、単に持続的に活用するという概念よりも幅広い作業である」
ラムサール名誉賞は、Dr. Luc Hoffmann。ラムサール会議創立者の一人であるDr. Luc Hoffmann氏は、1960年代初頭からWetlandsに関する国際条約の必要性を訴え、1971年に第一回ラムサール国際会議を開催し、爾来、この国際会議を常に推進する立場にあった。並行して、フランスのカマルグ湿原、スペインのコートドニャーナ、アルバニアのプレスパ、モーリタニアのバンクアーグインなど、象徴的なwetlandsの保全に指導力を発揮、同時に、WWF、Wetlands International、MAVA基金、FIBA、カマルグ生物科学センターThe Tour du Valatなどを創設した。「wetlandsは自然の中で重要な役割を果たしているが、賢明に活用されてこそ、その役割を発揮できる」 Dr Luc Hoffmannがラムサール会議で果たしてきた極めて重要な役割を、とうてい一言で説明することは不可能である。
控室でくつろいていた時間に、受賞者の経歴を眺めてみた。この年の受賞者5人のうち、Augusta Henriques(Guinea-Biseau)と、Thymio Papayannis(Greece)は、もう一人の受賞者Dr. Luc Hoffmann (Switzerland)の関係者だ。Dr. Luc Hoffmann氏は、アフリカ-地中海-アルプスという生態系を課題として、その環境研究と活動を支援するために、MAVA基金を設けた。Augusta Henriques(Guinea-Biseau)は、MAVA基金の援助を受けて自国の活動を進めた。Thymio Papayannisは文字通りDr. Luc Hoffmann氏をパトロンとして、MedWet/Mediterranean Wetlands Initiativeを過去20年間牽引してきた。
Dr. Luc Hoffmannの経歴に、カマルグ湿原の保全に貢献したと書かれていたので、
「私と辻井達一先生は、ラムサール会議の後、カマルグ湿原に旅をする予定です」
と話しかけたところ、Dr. Luc Hoffmannは秘書を招きよせて何かつぶやいた。秘書は私に、
「カマルグの自宅にご招待したいが、受けていただけるか」
と言う。
「スイスにお住まいではないのか」
と聞き返したところ、その秘書は「この人は何も知らないな」というようにあきれた顔をして、
「スイスにも自宅はあるが、カマルグ湿原の研究所にも家がある。ネットで地図などを送る。後ほどDirecteur GeneralのJean Jalbertに紹介する」
と言うので、
「Jean Jalbertにはさきほど会った」と伝えた。
辻井達一先生に事の次第を説明して、Dr. Luc Hoffmannに、ご招待をありがたく受け入れる旨を申し上げたら、嬉しそうに微笑んだ。
控室のソファーで
授賞式の夜、受賞者5人と、数人の関係者が町のレストランで食事を楽しんだ。辻井達一先生の隣にいるDr. Luc Hofmannは、秘書が押す車椅子で移動した。
***************************************
札幌に芸術の森というところがあって。若者の彫刻に植物を利用するというので引っ張り出されて手伝ったのだけれど、それにしても今の若いものは、突拍子もない発想ということをしないね。保守的というのかね。弁解めいて聞こえるかも知れないが、「年寄りくさい」んだな、発想がね。でも素直なところが取り柄でね、少しくらいキツイことを言っても凹まないんだね。前向きに聞いているよ。
帯広畜産大学の若い学生で、湖水地方みたいな企画に興味があるのは、たくさんいるはずだからね、少し若いのを送ってくれと頼んで、マンパワーとして活用したらどうだろう。学生も学校だけにいたって仕方がないしね。随分喜ぶと思うよ。
旭川の北の方にある下川町で、毎年一回、下川地域学会というのをやっている春日さんという人がいる。今流行っているだろ。地元学とか、地域学みたいな、あれね。今度一緒に行こうよ。
ラムサール会議が開催されたブカレストの会場前でタクシーを待っていた
礼文島の北の方に小さな湖がある。ミニホテルで「コリンシアン」。コリント風という意味だろうと思う。少しやりすぎだろうと思うくらい、コリント風に凝り固まった意匠でね。でも、湖側に張り出した舞台を作ってあって。一年中そこで何か音楽会をやっているはずはないが、時々ね。でも、趣向として面白い。研究所のニュースレターに、ラベッロの中空に張り出した舞台があっからね、思い出した。
霧多布に小さなバーを開かないかと、地元の人に持ちかけているんだ。漁師が住んでいた家が空家でね。漁師は潮風対策でアザラシの油を家の外壁に塗るんだ。アザラシの油は紫外線にやられるんだろうけど、すぐに真っ黒になる。これは捨ててしまえばボロ家だけど、それがこの土地の色だと思えば、魅力になると思わないか。それで、バーにして、週末だけ開けるのでも良いから、サカナは漁師なんだからみんなで持ち寄ってさ、酒だけ酒屋から買って出して。輪番制にして一人月に一日とか担当にして。俺だって担当を引き受けるって言ったんだ、だって、月に一度は何日か必ず行ってるんだから。そういう、共用資産の経営というのは、昔は田舎ならどこにでもあった。
オーストラリアには地下住居というものがあって。あそこは暑い地方で、半地下にして住居内の温度を下げようとしてる。でも、紋別の北方民俗博物館には、ギリヤークなんかの住居が再現されていて、それも半地下だ。北海道だから地熱を利用するために半地下なんだが。
ラムサール会議は3年に一度だが、出ていると分かってくることがある。理論ばかりで、口ばかりの人間も結構いる。学者風というのかな。現場では何もしていないじゃないか、という訳だ。でも、実際に行動している人は尊敬される。
COPというのは、contracting partiesつまり締約国という意味。国際条約会議だから、その条約に参加している国が締約国。本会議では各国代表、つまり外務省と環境省が前の方の席に座っていて、NGOはその後ろに陣取る。各国もNGOも手を挙げて意見を言う。NGOから国の代表に、「これを言ってくれ」と頼むこともあれば、国の代表が、意見を聞きに来ることもある。
国際泥炭会議International Peat Congress/IPCという団体がある。2000人規模。民間の会議だ。ルーマニア、ポーランド、ベラルーシなんかは今でも泥炭を燃料に活用している。泥炭を粉末にして土壌改良材にしてビートを栽培するとか、泥炭に粉炭を混ぜて固めて燃料にするというような技術、機械などの展示会もする。研究者との共同研究なども盛んに行われているから、研究者による発表会も開催される。
ラムサール会議には大学は来ないな。国際条約会議だから、学際的な発表の機会はない。生物多様性会議もそうだ。条約を広げたり、改良することなどが目的だからね。水田の問題なんかは、IPCでは取り上げないし、油椰子を熱帯の泥炭地で栽培しているけれどプランテーションで大規模栽培しているからいろいろな問題がある。こういうことを、ラムサール会議で課題にする。
地元のルーマニア料理を出すレストラン カルク・ベレ Caru'cu Bereで。健啖家らしい飲みっぷりはこれが最後だった。翌日から食が細り、酒類が喉を通らなくなった。辻井達一先生ご自身も、身体に変調を感じておられたと思う。旅とラムサール賞受賞式の疲れだろうと思いたかったが、以後、日本に帰るまでの3週間以上、旺盛な食欲は一度も戻ってこなかった。
IMCG/International Mire Conservation Groupは、カナダの大先生が作った団体で、人数を多くしたくないという趣旨で、50人くらいでやっている。多すぎると、一対一で話す機会が減るという意図だ。各国2人ずつ、米国は入れない。大きすぎる国は2人では役に立たないが、人数を多くすると主導権を取りたがる。米国はどこに出て行きても主導権を取りたがるね。だから嫌われる。米国は利権のあるところには必ず出てきて、ファシリテイターfacilitatorという立場で立ち回る。これはね、この立場だと会議の規準を作れる。米国にとって有利な規準を決めることで、自国の利益に結びつけることができる訳だ。だから、利権に結びつかない会議には参加しない。ラムサール会議は、締約国が資金を出し合って経営していて、日本は1番ではないが、かなりトップに近い。米国は一銭も出していないのではないかな。
国際生態学会INTECOL/International Ecological Societyという学会があるが、ここはIPC/International Peat Congressと一緒に研究したりする。
熊本の阿蘇に水準橋というのがある。これは、橋の真ん中で下の川に向かって水を放物線状に噴き出す。これが美しいね。何をしているかと言えば、水路の底に水が溜まるから、掃除をするためにはき出す。要するにドブさらいだけれど。用途に応じた工夫には違いないが、おそらくあれを作った人は、美しさということを考えたと思うよ。納まりということだね。無作為に近いが、何がしかの作為が美を生む。美しいということは、無理がないということでしょう。無理がないというのが良いよね。だって川の護岸をしても、台風がきて元の木阿弥になる。無理な護岸は美しくないんだ。直線の川は美しいとは言わないけれど、自然な川は美しい。無理がないんだよ。
北大植物園には設計図がない。350m角の植物園。実測図はある。初代園長だった宮部金吾先生が園路を作るのにね、20人か30人の人に頼んで、子供も年寄りも女性も男性も、自由に歩かせて歩きやすいところに杭を打ったという。その杭を実測して実測図を描いて園路にした。つまり、製図板に向かって線を引くのではなくてね、考え方を先に出す。人間というものは真っ直ぐには歩かない。トイレを作ると、そこに向かって、歩きやすい道ができる。だから、大通公園だって公園関係者が図面で道を作るが、人は必ず芝生の中などに道を作る。公園側は柵を作ってそこを歩くなというが、人はその柵を乗り越えて芝生を歩く。製図板で描く園路は無理があるということだろう。
昔、東京の神代植物園が北大植物園を調査に来た。それで、案内して説明した。そうしたら図面が送られてきて驚いたんだけど、北大植物園とまったく同じ園路が描いてある。説明をまったく理解してもらえなかったんだろうな。まったく同じなんだから。考えかたを伝えたつもりが、結果だけ真似た。
私は植物学だが、園芸植物のことは研究しなかった。興味はあるけど。それで、大学から植物園に配属されることになった時に、何十人か働いている技官にしめしがつかないと困ると思って、新宿御苑に一年間丁稚奉公に行かせてもらった。無報酬で置いてくれと頼み込んだら置いてくれた。蘭の植え替えとか、モグラ退治とか、庭園管理ならなんでもやった。でも技官が菊作りだけはやめておけと言ったね。菊は始めたら一年では到底覚えられないから。雨の日は仕事がないから、図書室に潜り込んで一日中本を読んだ。実に様々な本を読んだことが、自分の研究の形を作ったと思う。
北大植物園には少し長くいすぎたと思う、だって30年いたんだから。植物園はいわば病院務めみたいなものだ。教授と言っても講義を持つワケではない。植物園の管理責任はあるが。
薬学部というものは、薬用植物園を持たなければならないと法律で決まっている。北大薬学部の植物園が北大植物園の中にあったが、途中で薬学部の敷地に移動すると言って出て行った。それで考えて、その跡地を民族学植物園にした。ギリヤークやニブヒなどの年寄りに連絡を取って会いに行って、彼らが使った薬用植物をラベルに名前を書き込みながら、植物園にした。これは民族学の仕事かもしれないが、実に面白かった。
開発局が、新しく道路を作る時など、事前にコンサルに頼んで環境アセスをさせる。その報告書をもって来て、見てくれという。それで、地名サインを作るのに、アイヌ語表記を併記するように言った。今ではだいぶ徹底してきたね。ニュージーランドでは、マオリ語が上に書いてある。先住民に対する敬意だ。漢字はだいたい当て字だからね。先住民に対する敬意があった然るべきだと考えた。
今、平取にもアイヌ植物園を作らせているんだ。平取ダムの計画があって一度は凍結されたけど、町長は作らせたいんだね。沙流川は暴れ川だから。
それでアイヌの精神文化をフィールドワークするというテーマを決めて、地元のアイヌの若いのに、現場に年寄りを連れ出して聞き書きをさせている。家の中で聞いたって何も思い出さないんだよ。だけど、昔住んでいた場所とか、現場に連れて行くと、いろいろなことを思い出して、たくさん話が聞ける。ずいぶんたくさん報告書ができたから、今度は、人が読んでわかりやすいものにまとめるように言った。
アイヌ語に「IWOR」という発音、これは難しい発音らしいのだけど、「イオル」って言っているけど、泉靖一氏が古老に聞いて調査したもので、1952年に発表した「沙流アイヌの地縁集団におけるIWOR」という論文を読んで面白くて、ずっと覚えていた。それは流域圏を示す。このイオルには5家族が住める、この大きなイオルには30家族住めるという具合に、流域圏、まあ縄張りみたいなものだけれど。伝統的民族空間とでも言うのかな。これは日高地方のアイヌが使っていた言葉で、日高地方は日高山脈からたくさんの沢が流れていて、それぞれの流域を生活圏として。それで、自分のイオルで仕留めたはずの鹿が、手負いのまま隣のイオルまで逃げ込んだら、隣のイオルの首長に挨拶をしてから留めを刺して自分のイオルに持ち帰る。その際に、一方の肩の肉を礼に置いていく、というような具合だ。
道庁からアイヌ文化研究の座長を頼まれた時に、自分はアイヌ文化は知らないと言ったら、そこがいいんだと言う。何しろ、アイヌ研究者は地域を絞ってアイヌ研究をするから、アイヌから見れば、それぞれ偏った肩入れをするように思われて適当でない。それで、公平性を担保するために、素人が良いと。それで、泉靖一の本で読んだイオルの話を思い出して話したら、受け入れられて、それから随分イオルという言葉が使われるようになった。
河川をラムサール条約に登録するには、国交省が嫌がることがある。保全をしている途中で、保全に興味のない住民から、川が汚れるとか何か言われるのが嫌なんだ。でも最近は、「まあ、仕方がない」と思っているらしい。
渡良瀬遊水池がラムサール条約に登録したのは画期的だと思う。何しろ日本の公害問題の発祥の地みたいな土地だ。国交省は触れるのがイヤだった。でも軟化した。
ラムサール条約だけじゃない、初めてラムサール条約に登録しようと持ちかけられる地域の人々は、みんな、なんだか分からないものを押し付けられるような気がするんだ。みんなだ、全員だよ。でも、色々な努力をしながら、意味を理解していくんだ。つまり、自然環境を潰したら人間は生きていけないし、自然環境を活用して豊かに持続的に生き延びる方法と技術を開発する。
趣旨は、住民が行政を動かして、国際条約会議に提起させるという手順だ。今ではやっと行政が責任をもって保全するようになった。今は農業者の方が、意識が低い。首長は今ではまんざらではない。こういうのも案外使い道があるのではないかと思い始めた。
日本のラムサール条約を最初に提起したのは、釧路の開業医で札木照一郎/さつきしょういちろう。大変な読書家でね。当時、丸善が言うには、北海道の個人で最も本を買う人物という評価だった。議論していると、たぶん頭の中で英語の本のことを思い出したりするんだろうけれど、いきなり英語で話し始めたりする。趣味が広くて、万葉集とか日本文学も読み込んでいた。鳥が好きで、彼をパトロンにしていた研究者もいた。
ロータリークラブの会員で、どこかでラムサール条約のことを読んだのだろうね、その話をした。釧路湿原を登録しようという話を。そうしたら、王子製紙の工場で医者をしていた人物が賛成した。だから、日本のラムサール条約登録湿地は、行政でも、自然保護団体でもなくて、市民から始まった。
当時の釧路市長で鰐淵という人物が、後に国会議員になったが、なかなか先見の明があって、卓見というのか、この話に乗った。釧路は漁業と工業だけでは生き延びられない、これからはこういうこともあるのだろうと考えたんだな。それで釧路の財界が動いて、当時の環境庁を動かした。動かしたといっても、環境庁だって何をしたら良いのか分からない。だから私なんかのところに色々と聴きに来た。
札木照一郎が始めなければ、動きはもっと遅れたし、釧路はいつまでも誰も知らない釧路だったろう。環境省主導の活動になっていたかも知れない。
釧路新聞にいた佐竹直子という記者が、北海道新聞に引き抜かれて釧路版の記者をしていた。彼女がこの経緯を整理して連載したことがある。(注)
釧路はラムサール条約登録と同時に、釧路でラムサール会議を開催した。これでラムサール会議の流れも変わった、画期的なできごとだった。釧路湿原の名前も、日本だけじゃなくて、世界中に知れ渡った。
(注)北海道新聞釧路根室版連載企画「不毛の大地母なる大地(2007 年 6 月~2008. 年 10 月 全 58 回)」執筆者は佐竹直子記者
いわゆる先進国にとってみると、湿地の再検討の段階で、こういうことが始まった。発展途上国は先進国が経験を踏まえて、「前者の轍を踏むな」と言っている。欧州は泥炭で燃料を作る、泥炭を資材として使ってきた。西欧は新しい採掘を禁止し始めた。スコットランドでも、ウイスキーの燻蒸に使っているスコットランドなのに、これ以上掘るなという人も現れた。
ミズゴケは、日本は年間20万トンくらい世界中から輸入している。主に園芸用だ。蘭の業者が使う。蘭という植物は、元々ミズゴケの中に生えているような植物だから。カナダが主な輸出国だが、制限を始めた。ニュージーランドも手一杯。今はチリから輸入しているけれど。それなら栽培したらどうだと思って、ミズゴケの試験栽培を開始した。泥炭の成長は一年に1ミリくらいだが、ミズゴケは10センチも20センチも成長する。九州の東海大学が放棄水田や減反した水田を使えないかと考えたんだな。ミズコケは水だけで生育するし、水面にイカダで浮かべておくだけで良い、貧栄養状態が良いのだし、除草の必要はないし。でも、農家というのは、手がかからないというのを信用しないというか、嫌だというのか、耐えられないらしいね。何か一生懸命に取り組まないと気がすまないんだろう。なかなか手を上げてくれないな。自然栽培というのは一種の農業革命だろう。でも農家というのは、やったことがない栽培方法には手を出さないし、作ったことがないものを作るのが嫌いだね。
農家はね、自然環境の大切さは分かっている。だけど、過去の経緯もあるし、自前で収益のあがる新しい農業の方法を考えるなんて至難の業だ。だから声を上げて、自然環境を守れ、農業収入があがる方法も提案しろ、と自治体を突き上げて、ラムサール条約登録をさせて、困難な予算は締約国なのだから国に補償させる、そんな運動を起こしたら良い。
ラムサール条約会議というのは、これまでできなかったことを、国際世論を背景に可能にする場だ。各国の利権が絡む場というよりは、締約国の威信が問われる。ある水準が維持できないと、イエローカードが出される。それでも改善しなければレッドカードで退場だ。これまで、現場の農家や地域の人々が、自然を守れ、生活水準を補償しろと立ち上がって訴える相手は、国や自治体だけだった。でも、ラムサール会議はNGOが手を挙げてモノを言える場だ。これを活用しない手はないよ。面白いし、やりがいはあるし、難しいけれど。
他の会議は、例えばワシントン会議などはもっと利害が絡むからギスギスしている。でも、生物多様性会議とラムサール会議は、使い勝手がある。湿地を抱えた地域社会にとって生き残りのメディアとして使えるんだよ。縦割り行政を横断して使いこなせるかも知れない。
地域社会も企業もNGOも、この会議を戦略的に使って、世界世論を背景にして、政府を動かす場としても使える。エビアンなんて、スポンサーだが、この場をうまく使っていると思うよ。日本の酒屋なんてどうだろう。水資源のこと、興味ないか。鶴という名前をよく使うでしょ。あの鶴はみんなタンチョウだろうね。ナベヅルじゃないよ。それなら、やっぱりラムサール会議だ。
**************************************
Thymio Papayannis氏 (78歳) はギリシャを代表する景観建築家だ。ラムサール会議の常連で、今年のラムサール賞受賞者。ギリシャと言えば、イタリアと同様、古代国家隆盛の地、近代建築思想を遡ればこの国にたどり着くのだが、ご承知のように今や経済が危機に瀕していて、近代的な経済発展主義、過度な消費主義に対する猛烈な反省がある。
辻井達一先生と一緒に頻繁にお目にかかるうちに、君もランドスケープ建築家だったら、一度ランドスケープの話をしようか、ということになって、ゆっくり話をした。
以下は、『Thymio Papayannisとの対話』。
****************************************
アメリカボストンのマサチューセッツ工科大学を出てギリシャのアテネで職業としての建築をしていた1984年に、政府からラムサール条約湿地に登録されている湾岸地域の保全計画を依頼された。WWFとラムサール会議創立者の一人Dr. Luc Hoffmannに出会うが、スイス人のHoffmannがギリシャの湿原に興味をもっていることに刺激されて、自然保護の研究と活動を開始した。特にギリシャと地中海地方で、Wetlandsの保全と活用と文化に優れた指導力を発揮し、ラムサール会議では25年の活動を続けてきた。Dr. Luc Hoffmann氏と共同で、ギリシャと地中海地域に多くの環境団体、研究機関を設立した。特にMedWetの立ち上げに10年以上の間決定的な仕事を果たし、今も相談役として貢献している。彼の仕事と著作は、Wetlandsの価値を人々に教え、特にWetlandsの文化的価値を会議に紹介したことは独自の仕事となった。「Wetlandsが潜在的に持つ資源を活用することは、人間の知性の進化に結びつく。人間とWetlandsの関係を構築するという概念は、単に持続的に活用するという概念よりも幅広い作業である」
設計をする時に、デザイナーは「美しい」ということを前面に出して仕事をするが、その前にやらなければならないことがある。自然環境を読み取る、生物社会の仕組みを構築する必要もある。建築物のデザインの前に、ランドスケープの設計が常に必要なのだが、そうはならないのは、施主にそれだけの見識がないからだ。アテネオリンピックの時もそうだが、政府の仕事をする際にも、常にその主張を続けてきた。
日本はどうだ。ランドスケープを建築と切り離して教えているか? ギリシャでは、大学で生態学、生物社会学などの大切さを教えないから、建築科の学生は構造と美意識だけを追いかける。生命についての見識を教える必要があるのだろうな・・・
ランドスケープ建築家も、土木建築の建築家も、ラムサール会議に参加して来ないのが不思議だ。君の研究所が、日本で内海のWetlands Initiativeを企画している? それなら、MedWetと連携しよう。世界の内海生態系戦略と連携することは、MedWetの主旨に適う。私が日本に行くよ。君がギリシャに来るのなら、9月にアテネでランドスケープと自然生態学の会議を予定しているから、参加しないか・・・
**************************************
風景造形に関する姿勢は、基本的に同意できるものであった。工学者たちは、機械的工学論で現在の世界が直面するすべての課題を解こうとしているように思われる。だが、それはまったくナンセンスだ。自然世界の本質と全体について論じているのに、鳥や、昆虫など、一部の分野の研究に没頭している研究者が、その研究で世界の本質も全体も解き明かすことができると嘯いているようなものだ。機械的土木工学の世界には、戦後、膨大な資金が流れ込み、優秀な人材が流れたので、世界の管理者たる強い自負もあるだろうが、工学と美学という乏しい言語で自閉する姿は、近代の病そのもののように思われる。
この問題意識は、Thymio Papayannisと共有している。
それでは、風景構築が自然観の具現化であるとすれば、ギリシャ文明の快楽主義から、果たして、現代の建築家がどこまで民族の思想の転換を果たしているのか。ロゴス中心主義と、ギリシャ神話に見られる多元的な世界観と、現代のギリシャの物語は、どんな関係にあるのか。カザンツァキスの一連の小説や、アンゲロプロスの映画を思いながら、彼の言説の背後を探った。Papayannis氏は、自然と人間の関係をエンジニアリングの方法で捉えているように思われた。どちらにしても、現代ギリシャを代表する景観建築家が、ラムサール会議で「Wetlandsと文化」という講座を押し進めているという「風景」は、強く印象に残った。
日本を含む東アジア地域で、新しくラムサール条約に登録した地域のNGOや首長が、状況報告をした
1960年代と言えば、世界的にカウンターカルチャー運動を知識人が唱導した時代である。
特に欧州のそれは、17世紀のグローバリズム以降、世界を植民地化した欧州による帝国主義的支配体制を痛烈に批判して、体制を変えようという運動であった。近代主義に対する批判も激しく渦巻いた。自然環境という課題は、直接政治に対してモノを言おうとする活動に限界を見出した人々が選んだ道の一つだ。日本では、有機農業の世界にも、多くの若き政治青年が向かった。
今回のラムサール会議で名誉賞を受賞したDr. Luc Hoffmannとその仲間たちは、60年代に自然保護の立場から湿地の重要性に着目し、「体制に回し蹴りを食らわせる」道を、飛翔する道fly wayに見出した。自然環境保護において、渡り鳥という存在が注目を集めるのは、渡り鳥の生態系は、大きく国を超えて成立していて、渡った先の環境が破壊されてしまえば、その生態系は壊れて生存が難しくなる、つまり無作為な複数国間の連帯が必要になるからである。この渡り鳥という象徴的な生物を媒介とすれば、湿地保全の会話を国際間で始めることができる。その結果として、条約として理念と規則を共有するという意識と行動にも、結びついて行った。
自然環境は大切だ、というマクロ理論には誰でも賛成だろう。人間の活動と、自然資源との収支が、消費過剰であるという説明には、誰でも頷くはずだ。だから渡り鳥の保全を通して、国際社会が自然環境保護についてその規準を話し合い、国際会議で協定を結ぶ。
そこまでは良い。「総論賛成、各論反対」の定石が、ここにも適応される。
北海道湖水地方(十勝海岸湖沼群)でも、同様だ。総論の理想を追って、現場の実状を考えずに法的な網をかけられたら、地元に暮らす人々は手足を縛られて貧窮する。
辻井達一先生が書いた『湿地と貧困』という小冊子を、柏林講座で取り上げたことがある。冒頭に、以前とあるラムサール会議でインドネシア代表が欧州の代表に向かって、こう言ったとある。
「湿地の保全が大切なのはわかる。欧州は、自分たちの失敗の轍を踏ませたくないという。だが、インドネシアのとある湿地の周辺に住む住民は、鳥をつかまえて、一年間に2万トンのタンパク質を手に入れて生き延びている。湿原の動物を保全しろというのなら、このタンパク源を用意してくれ」
これが各論の象徴的な議論である。簡単に言えば、総論を実現するために、各論をどうやって解決するか。これは各政府に課せられた課題でもあるが、地域のNGOは、ラムサール会議に参加して、世界の情勢を把握し、人間関係を築き、地域の目の前にある各論に対する対策を講じるべく考え始める。
Business, Water and Wetlands - the role of the private sector in conserving and restoring wetland areas. Lead organization : WWF 今年の会議では、このような各論を提起する42の会議が開催された。
魅力的なのは、ラムサール会議が、「湿原の保全とその賢明な活用」という主題を掲げたという点だ。自然保護だけを訴えたのではない。会議の当初は自然動物の保護という観点に集中していたが、各国の参加から学び、人間の暮らしを豊かにすることを通して環境の保全に向かうというWise Useという概念を提供したというのは、卓越していた。最近の数十年は、自然科学的な研究よりも、本来の、湿原を「活用する」という点に重点が置かれている。つまり、湿原のある「地域振興」をひとつずつ実現していくことが、総論の実現につながるという考え方だ。
この課題は、国の大小、経済力、軍事力の強弱と一線を画して、地域どうしが対等の立場で議論すべき課題である。ラムサール会議は、当初、欧州とアフリカの関係構築から始めた。60年代という時代は、欧州諸国の植民地であったアフリカ諸国が、次々に独立を果たしていった時代だ。しかし、各国は植民地を手放すにあたり、プランテーション経営などを支配する企業体を、根深い組織として周到に各地に植え付けた。その収奪が欧州社会の物質的豊かさの基礎であり、アフリカの大地はその収奪の影響で、今もなお生態系を破壊され、荒廃の極みに晒され続けている。それは今でも変わらぬ問題、その根は深いのだが、湿原の保全の課題は、旧宗主国と植民地という関係を解体して、利権が絡まない環境の課題として語り合うことができる格好の主題。むしろ、アフリカの大地の荒廃に対して、世界の世論を導くこともできる。
当時のソ連とアフリカを往復している渡り鳥もいることから、ソ連を含めた国際的な協定の実現にも努力したようだ。しかし、小林聡史釧路公立大学教授の解説によれば、1968年のプラハの春では、これで準備していた国際条約締結構想はすべて粉塵に帰すと、Hoffmannを含めた創始者達は落胆したこともあったようだ。1971年、彼らの長年の努力が実り、ついにカスピ海に面したイランのラムサールという町に、各国政府代表や専門家が集まり、世界中の国際的に重要な湿地を保護するための国際条約を締結するために国際会議が開かれ、この条約が誕生した。
今年の会議で名誉賞を受賞したDr. Luc Hoffmannは、その創始者の一人である。辻井達一先生が「上流階級の知識人」と称したこの創始者が何を考えたのだろうか。
まず、Hoffmann氏の考え方を示す資料を読んでみよう。フランスのカマルグ湿原保全に関する資料だが、考え方の基本はこれで分かる。
Is it possible to protect wetlands for their biodiversity, while at the same time improving the living conditions of the people who live there?
Our commitments and the results obtained over recent decades show very well that there is no incompatibility at all between nature conservation and development. Good management must take into account the range of human activities just as much as factors favouring the health of the ecosystems. If this is successful, it can guarantee the support and promotion of biodiversity at the same time as sustainability of use. The point at issue lies in management for biodiversity which must go hand in hand with the inevitable development of human activities. This could involve the cessation of former practices in favour of the establishment of new methods.
The Tour du Valat has contributed to the conservation of species and ecosystems, both in the Camargue and around the Mediterranean. Nevertheless, this has not prevented us from being of assistance to landusers. Thus, the work which we have carried out within the framework of agri-environmental measures has helped to open up new prospects for farmers. With rice growers in particular we have explored alternative methods of cultivation which have the advantage of being more sustainable.
Our participation in international waterbird research networks has contributed to a better understanding of their status for the rational management of their populations. We note for example the establishment in recent years at the Tour du Valat of a wintering population of Greylag Geese. Wildfowlers are to be counted among the principal beneficiaries of these developments. The studies undertaken by the Tour du Valat on the life cycles of fish contribute to improved management of fresh waters, favouring not only the health of the ecosystem but also the well-being of the fishermen. The case of the Prespa Lakes in Greece provides an example. The potential for opening wetlands to the public in the way we have initiated at the Marais du Vigueirat in the Camargue is also capable of contributing to the prosperity of the inhabitants of such sites, provided the arrangements are compatible with the healthy state of the ecosystems.
These examples, to which others could be added, demonstrate the potential for partnership offered by the collaboration between researchers and users of wetlands. The potential is still poorly recognised at present by the users, despite the many contacts initiated by the Tour du Valat with professional associations, local authorities and Government departments. It is now a pivotal aspect of our work. Luc Hoffmann
自然保護と、人間社会の経済や文化の発展は、本来、齟齬を来さない。人間もまた生物社会の一員であって、生態系を健全に育て維持するためには、湿地を保全するだけではなく、積極的に活用することで、人間と自然環境の経営を実現することができる。生態系の持続的な維持が可能になればこそ、その利用も持続的に可能になる。湿地の利用といえば、なによりも農業思想と技術の開発と実用化ということになる。人も自然も豊かに生きられる社会環境を形成しよう、という考え方が書かれている。
本会議場。各国代表、日本代表の場合は外務省と環境省が参加し、その後方にNGOが列席している。事前に条約の課題に関する議論があって、たたき台となる案をもって、この会議に参列する。そこで各国の考えを提示しながら、落としどころを探していく。最終日には、成果としての修正条項を発表して、会議を終了する。
湿地(wetlands)と言う言葉は、幅広い意味を持った造語で、干潟や湿原はもちろん、川でも湖でも、珊瑚礁でも湿地に入る。海については深さを限定しているが、湖はどんなに深くても全て湿地だ。大きく分けると、法的な保護が十分されている湿地を登録湿地とする厳密な考え方と、ともかく国際的責務から価値のある湿地を登録して、保護策は後から行う国がある。日本は、どちらかというと前者の厳密な考え方をしている国で、具体的には、国設鳥獣保護区の特別保護地区として法的保護が担保された場所を登録湿地としている。
北海道湖水地方、つまり、十勝海岸湖水地方の場合、この鳥獣保護区の制定について、住民から反論がある。鳥獣被害によって離農者が絶えない土地で、住民の意見も聞かずに、わざわざ鳥獣保護区に指定させてから登録するラムサール湿地とは、いったい何か、と。一般社団法人湿原研究所は、農業生産法人大樹農社とともに、すでにこの地域の一員となり、この地域の振興を計画している。当然、住民の損害状況を代弁する立場にある。生態系の保全が必要なことは、農業者も理解しているが、その保全の方法を、何を以て行うのか。行政は鳥獣保護区に指定して、一方的に義務の遂行を求めるだろうから、住民としては先手を売って、住民と土地の自然環境維持のために必要な政策について提言する。そのために研究所がある訳だ。
総論を担い、ラムサール条約登録湿地の数を増やすという閣議決定に従って霞ヶ関が動く。しかし、近代憲法が権力の暴走を縛るために制定されているように、私たち現場の農家であり生活者は、保全活動のつけを現場に回されては困るのだから、そうならないように、国際世論の動向から学びながら、異議を申し立てる。政府が反応しなければ、ラムサール会議の理念で理論武装して、繰り返し異議を申し立てるべきなのだ。
Valuing wetlands - Capturing economic benefits from wetlands wise use. Lead organization : UNEP & IEEP/TEEB.
上記の写真の会議「Valuing wetlands - Capturing economic benefits from wetlands wise use」は、湿地の価値を分析して、それを経済価値、特に金銭に置き換えてみようという試論を展開する内容であった。提案そのものは生硬で初歩的なものだったが、それを聞きながら考えた・・・果たして北海道や環境省は、湖水地方に鳥獣保護条例を適応するに際して、経済効果のアセスメントをするのだろうか。つまり、国設鳥獣保護区指定をした場合の経済効果の試算。もし、しないのであれば、それをしよう。その数字がマイナスであれば、その数字を以て、当局と闘おう。それが公平な社会というものだからだ。
辻井達一先生にその点を問いかけたところ、
「地元の農協が数字を出すことはあるが、第三者にアセスメントをさせたことは過去に例がない。それは面白い、ぜひやろう。それがあれば、闘えるよ」
在ルーマニア日本国大使館が主催した懇親会の席で、同席した環境省のスタッフにもその件を話してみたところ、
「それは過去に一度もやってこなかったけれど、やるべきことです。とにかく始めてみることが大事だと思う」
という反応である。
北海道湖水地方の生花地区には、60年代に80戸の家族が住んでいたが、今は、農家だけで6戸。晩成には40戸の農家がいたが、今は4戸。離農者が続出した結果である。夏に海霧があがる湿原地帯経営が、これまでの経営手法では無理なのだろうとすれば、経営手法の再開発の場として、ラムサール会議に提起される実に様々な角度から提起される、「湿地の賢明な活用」案に耳を傾けてみるのは、大いに役に立つと思われる。
***********************************
ルーマニアのヒマワリ畑で
ラムサール「科学賞」というものをもらったんだけど、やっぱり「感慨」があるねえ。どんな賞をもらうよりも一番うれしい。大学の教授から湿原をやれと言われて始めたんだから、まだラムサール条約が生まれる前から湿地をやってきた。でも、別になんですか、期待していたワケではないが、もらってみれば、私としては一番うれしい。
天邪鬼かも知れないけど、僕は、生まれは東京神田、でも4歳から大阪に引っ越して。だから、東京の上品さも、大阪の現金さも身につけたというのかな。時々、関西の人間とメールでやり取りするときに関西弁で書く。すると、そこは違うなんて直されるけど。つまり、自然保護というと東京の観念というか何か照れくさいような、で、賢明に活用して金儲けなんて、大阪風だと思う。どちらもね、身についているというのか。
東京は、特急と言えば、車体も良い、立派、豪華・・・。大阪はね、速く走る奴が特急。宝塚に行く電車だったかな、今でも戦前の車体を走らせている。感動するけどね。まあ、おんぼろだ。でも速く走る時は、特急。
湿原も一緒かな。大きさではなくて。2haでも、2000haでも、良い。大切なのは中身でしょ。
中村玲子ラムサールセンター事務局長と
ラムサールセンターの武者孝幸さんはね、名刺に副会長兼ジャーナリストと書いてある。若い時に新宿で出版の編集プロダクションで編集者をやっていた。自然保護の仕事をしている中村玲子さんに出会って意気投合して、それで中村さんに事務所の一室を貸していた。でもそんなことをしていたからかな、商売が左前になったんだね。主客転倒して。
中村玲子さんは、自然保護の仕事に出会って、ラムサール会議にも出るようになった。それで今は、ラムサールセンター事務局長。ご両親の面倒も見ているから自宅の2階の一室を事務所にしていてね。一人座っていると、ドアを開けて何か入るのに、座っている人に立って動いてもらわなきゃならないような小さな事務所。自宅の2階の一室、6畳とかそのくらいじゃないかな。外国から来た関係者を連れて行くとみんなびっくりする。自宅の2階にね、階段をあがっていって、ここが事務局だというと、びっくりする。
編集ができるから環境省も仕事を依頼したりするが、それでもこの人を取り込もうとは思わないのかな。本人がその気がないのか。だから独立独歩のラムサールセンター。でもね、この人が世界中の誰も彼もから信用されている。格別に信用されている。
旧市街のルーマニア料理店Caru'cu Bereで
若者にはいつも色々説教するんだ。考え方が縮こまっていて仕様がない。今の役所は、上の人間が教えないんだろうな。一生懸命に聞いていたが。何にでも関心を以て、自主的に価値観を持ってね・・・・そういうのがないんだな、今の若いものには。だから一生懸命に言ってやるんだ。
ラムサール会議では、アジアには発展途上国があるからね。欧州はアフリカとの関係だ。かつての宗主国と植民地の関係が今も生きているね。フランスの植民地だったところは、やはりフランスと組む、というふうにね。アメリカは特殊だ。存在が薄い、というか、軽いというか。南アメリカ諸国は、アメリカが出てくると宗主国面するから、嫌がるんだ。
欧州はね、戦後、欧州の知識人は自然保護のことを考えたんだな。日本も大きな金を出している。条約ですから窓口は外務省。今回の会議には、外務省、環境省、農水省、国交省が参加している。ロシアも出てこないね。シベリアのハンカ湖は、あのデルス・ウザラという記録文学があるでしょ、その舞台だ。タンチョウが渡る。森林伐採がどんどん進んでいて。伐採して光が入ると、永久凍土が溶けて湿地になる、沼にね。沼になれば、種が落ちても発芽できない。森林の再生は難しくなる。こういう問題がある。それでもロシアは出てこない。北朝鮮と連携しているのかな。そう、今年は北朝鮮が会議に来ていたな。
ドナウデルタをクルーズした
ドナウデルタの旅の仕上げに、冷たい白ワインとキャビアをいただいた
ニッカの竹鶴氏が北海道環境財団に相談に来たことがあってね。あそこは江戸末期に広島の造り酒屋「竹」といったそうだ。広島の竹やぶにタンチョウが巣を作ったことをきっかけに「竹鶴」と称したというんだね。それは違うだろうと言った。だって、竹やぶでは、羽を広げて飛ぶこともできないからね。でも、そういう話。ともかく、鶴に世話になったから、「鶴に恩返しプロジェクト」。鶴の数を増やそうという事業をやりたいと。
水はね、安全な飲み水の確保が難しくなった。昔は日本を一歩外に出たら、生水は飲めなかった。今も同じようなものだが。特にアフリカを中心に、家畜のし尿、野生動物の死尿の汚染、ビクトリア湖ではエイズが魚から伝染する。プランテーションで大企業が大量に農薬を散布するとかで汚染されたその水を地元の人が飲む。安全な水が飲める国は、ごくわずか。英国、独国、フランスの一部、北欧、それ以外はあてにならない。アジアは日本以外は怪しい。
ラムサール会議はね、この会議の場を使って、今まではできなかったことが、できるようになった。そういう事なんだ。
***************************************
7月15日から17日まで、今年のラムサール名誉賞を受賞したホフマン氏Dr. Luc Hoffmannの自宅に、辻井達一先生と二人で逗留した。南フランスにあるカマルグ湿原だ。
1923年にスイスに生まれたホフマン氏は、戦争中はスイスで鳥類学Ornithologyの学生として過ごしたが、戦争が終わるのを待ちかねてフラミンゴの居留地として知られる南仏のカマルグへ向かい、湿原に魅せられて、この研究所の元になった農場The Tour du Valatを購入した。1947年のことだった。
現在のカマルグ湿原に生息するフラミンゴ。茶色の鳥はヒナ。日本のタンチョウなどと同様、終戦直後には絶滅直前の状態にあったものを、戦後の地中海湿原研究所の努力が実り、復活した。
カマルグ湿原は、ゴッホの「アルルの跳ね橋」という絵で私たちに馴染みのある、プロヴァンスのアルルという町を北の起点として、南の地中海まで、約930平方km=93,000haの広さを持つローヌ川デルタ地帯で、西ヨーロッパ最大の湿原地帯である。
「谷間の塔」と訳すべきか、The Tour du Valatは、その後農地と湿原を買い足して現在では2,600haを超える敷地を持ち、スイスのLa Roche社創業一族であるホフマン氏の資産を元に運営する民間の研究所として、地中海地方のwetlands研究活動を推進している。農場の名前The Tour du Valatがそのまま研究所の名前として広く世界に知られているが、ここでは「地中海湿原研究所」と称しておこう。
The Tour du Valat地中海湿原研究所 研究施設の俯瞰写真 同研究所ウェブサイトから転用
ホフマン氏は、カマルグに居を構えて研究を進めるうちに、湿原生態学Wetlands ecologyの重要性に気づき、研究所設立後、長くこの研究所の代表者として活動を続けてきた。90歳を超えた現在は一線を退き、この研究所の敷地内にある住まいと、スイスの自宅を往復しながら余生を送っている。
ホフマン氏と話し合ったことは、以下の通り。
1. 私たち一般社団法人湿原研究所と地中海湿原研究所は、姉妹関係を目指して共同研究関係を構築する。
2. 地中海湿原研究所が、ギリシャのティミオ・パパヤニスと連携して、過去20年間、構築の努力を続けてきたMedWet/Mediterranean Wetlands Initiative地中海湿原戦略構想会議の、経験と構想の骨格を借りて、私たち一般社団法人湿原研究所は、北海道を中心とした北東アジア地域における、North-eastern Asia Wetlands Initiative北東アジア湿原戦略構想会議の発足を目指す。
7月14日夕方 ホフマン氏宅応接室にて
この会議は、私たちが到着した14日日曜日の夕方、ホフマン氏の自宅の応接室で行われた。
翌日15日月曜日、朝食の席に到着した、現在の地中海湿原研究所の代表者であるDirecteur General Jean JALBERTジャルベール氏に、ホフマン氏から事の次第の説明がなされた。ホフマン氏は、ジャルベール氏にこのように伝えた。
「彼らは、MedWetの構想を展開して、北東アジアに湿原戦略を構想する。ロシアのシベリア、アメリカ合衆国のアラスカ、中国の北東部、北朝鮮、韓国、日本に囲まれた北東アジアを、北海道に拠点を置く研究所が、wetlandsを基礎にした一つの生態系としてまとめる。これは、なすべき仕事だ」
さっそくジャルベール氏と私が工程を相談し、その日の朝食後、研究所の会議室兼研修室において、午前中すべての時間を使って、具体化作業について話し合いに使うこととなった。
図書館兼会議室に続く小道の入口
この研究所用地の前身は、Tour du Valatという名のワイン農場である。
1930年代にフランス全土のぶどう畑が感染症によって壊滅した際に、この農場の畑がローヌ川の氾濫によって水で覆われたために感染から逃れた。この土地は湿地だから、決してワイン用ぶどう生産に適してはいないが、その時期、フランスで唯一のワイン生産となったために、大繁盛した。ホフマン氏が買収した頃には、すでに凋落していたが、豊かな時代に作られた施設は比較的強健で、ホフマン氏一家が住む屋敷も当時の農場主の家を改造したものだし、その他の農場の建築物はそのまま内装を変えるなどして、現在も研究施設等として使用している。
研究所に展開する以前には、農家が共存していたために、この研究所建物は、学校として使用されていたこともあり、小さな「村」の様相を呈していた。
敷地内は、今も至るところに農場としての機能が生きている。井戸水汲みポンプと、その隣の家畜用水桶。馬車。農作物栽培実験用農場、家畜小屋は研究員の集会所や研究室、古い羊小屋は改造して、研究のための長期滞在者用宿舎として使われている。
外観は家畜小屋をそのまま維持し、内装に手を加えて研究施設の一部としている
左からProgramme Director Patrick GRILLAS氏、Directeur General Jean JALBERTジャルベール氏、
辻井達一先生。会議研修室棟の前で
この会議は、辻井達一先生と私、そして、ジャルベール氏と、研究所の経営第2位の地位にある研究課題責任者Programme Director Patrick GRILLAS氏と、計4人で、午前9時から正午まで行われ、その結果、以下の4点で合意し、共同作業の可能性を探ることになった。
1. 水田耕作技術交流 カマルグ湿原では戦後水稲栽培が約50年の間続けられてきたが、雑草防除と駆除、害虫駆除、施肥、これらの化学農薬、化学肥料の使用が、下流域に位置する湿原自然生態に被害を及ぼしている。数千年におよぶ水稲栽培の歴史と技術、近年の有機栽培思想と技術の発達をもって、日本から協力できることがあると考えられる。地中海湿原研究所の研究資料等をインターネット等で日本に送付し、日本側がそれを読み込んで、課題点を指摘することから作業を開始する。
2. 放牧による農地と自然環境経営論 grazing management
3. 湿原再生技術 wetlands restoration
4. 北東アジア湿原戦略構想会議NEA Wet / North-eastern Asia Wetlands Initiative構築に対する、研究機関としての協力(戦略会議構築運営は、ギリシャにおいて、パパヤニス氏を指導者として行われている)
旧家畜小屋。現在の図書館bibliotequeと研修会議室棟
会議に先立ち、Directeur General Jean JALBERTジャルベール氏が、地中海湿原研究所の概要について説明した。
地中海湿原研究所図書館。地中海湿原研究に関する資料が、豊富に整理されている。他の研究所の間の紀要の交換なども、ここが中心となって機能している。
午前中の会議後にはホフマン氏が参加して、会合の場を近くのレストラン移した。
プラタナスの枝葉を棚作りに誘引した気持ちの良い木陰で、湿原の活用、とくに農業と自然環境経営との関係について議論が進んだ。政府は食料生産に関する国家的なグランド実現の方途として補助金を使い、農家は往々にして補助金のための農業に邁進する。そこに落とし穴も活路もある。
広大な干潟に、アッケシソウの群落が至るところにみられる
午後は、フラミンゴ研究者に案内されて、湿原を歩いた。
このような干潟は、九州型と言うべきだろうと、辻井達一先生が言った。
The Tour du Valat地中海湿原研究所入口の門
ホフマン氏は、知識人として、そしてパトロンとして、欧州社会における戦後の自然保全活動に重要な役割を果たした。また、ラムサール会議だけでなく、WWF、Wetland International等の創立を主導した人物として、そして、その人格の豊かさに対する愛情を含めて、関係者から深い敬意を集めている。
幾つかの対話の中で心に残ったのは、当初ホフマン氏は、絶滅に瀕していたフラミンゴの保護のために、この農地と湿原を購入したが、しかし渡り鳥の保護のためには、それだけでは十分ではないと気づいた。渡った先の自然が破壊されてしまえば、生態系は成立しないのだ。国際間の条約の必要に目覚めたのは、このような議論を、若い学者が集まって交わした結果だった。
「社団法人湿原研究所の基金をどうするのか」という問いかけで始まった対話もあった。「政府から研究費を得て運営するのか」と。私立研究所として、年に2千万から3千万円程度の予算でまわすのであれば、企業の付属研究所という位置づけで完結できるだろうと思っていたが、今後、地中海湿原研究所との共同研究を進めるのであれば、一桁上の資金が必要になり、それは私立研究所では収まりきれない。
ホフマン氏によれば、
「Mava foundationという基金があって、地中海湿原研究所の年間5億の予算の約半分近く、つまりおよそ固定費分を自前で賄っている。もっとも施設費などの当初予算も、その減価償却費も含まれていないが」
Mavaはホフマン氏が作った財団である。地中海湿原研究所は、年間予算の約3割弱を国や自治体の研究を受け入れているけれど、自前の資金で研究所の基礎を固めているから、それはあくまでも自立した研究所として引き受ける立場を確保できる。
「アジアから申請できるのか」との問いかけに、「この基金は、アルプスと、地中海と、西アフリカ地域に限って出資する基金である」との返答であった。
「詳しくは、ジャルベールと話してみてくれ」
後にジャルベール氏とMavaについて話し合ったが、
「地域の生き残りのために作られた基金だから、他地域に助成することに積極的ではないが、欧州とアフリカ地域の生態系保全のために、他地域との連携が必要となれば、他地域にも資金を投入するだろう」との由。
辻井達一先生と語り合ったのは、ホフマン氏のような上流階級の教養人の存在について、である。欧州で生活をすれば、招き招かれる機会のある、いわゆる上流階級の人士だが、成金趣味や俗物趣味の臭みのない人柄と、教養の質の高さには感服させられるものだ。
英国18世紀に登場したMen of lettersという人物群像は、俗に文人と翻訳しているが、一様に上流階級に属している。英国近代の理念と精神を支えたと言われる人士だが、彼らがmen of lettersつまり、言葉の人でなければならない理由は、言葉はその背後に膨大な潜在的文化世界を蓄えることを意味する。誰もが使うメディアだから、共通の世界観を作るためには、言葉だけが力を持つ。現実世界は、言葉を手掛かりにして動き出すと言っても、言い過ぎではないほどだ。
わかりやすい例を挙げれば、資本主義capitalismという近代的な社会思想は、大英帝国経営の思想そのものとして誕生し、機能してきた。資本を投じた資本家が一群の指導者として指揮権を握る社会には、階級が今も厳然と存在する。一群の人々に対する生殺与奪権を握る支配階級はエリート教育を受け、自覚を叩き込まれて社会を支配する。だから、第二次世界大戦でも、英国の軍人で戦死した者の比率は、上流階級が実に多かった。彼らは、国家を守る前線に立つ覚悟を叩き込まれていたからだ。
しかし、ここで考えなければならないことは、彼らが守ろうとしたのは「国家」、しかも、自分たちの階級の利権として構築した「国家」であって、「国民」ではないという点である。彼らは、上流階級の誇りのために、そして、上流階級が作った国家を守ろうとして死を賭す。近代国民国家Nation Statesを作った彼らが、みずから作った国家を守る。決して、彼らとは違う階級にいる99%の庶民の生活と富を守ろうとしたということではないということだ。
近代経済学者宇沢弘文氏は、上流階級の子弟を教育するケンブリッジやオックスフォードを支える財政基盤について明らかにした。彼らの基礎財政は、常に、国家とともに画策した、他地域からの収奪による富によって支えられ、その富を持続的に維持することが、学問の目的だったのだ。
そして、英国という国家と、近代資本主義下における企業の構造は、まったく同じ構造に作られている。資本家は投入した資本を守り育てるために、企業を動かす。企業を作るのは資本家である。だから、資本家と被雇用者の間には、厳然とした階級差がある。これが西洋近代の本質だ。
一方、日本の近代を準備した江戸時代の近世社会は、果たして、西洋近代のような骨格を持っていただろうか。内村鑑三が『代表的日本人』に描き出した上杉鷹山は、西洋近代の文脈で言うところの上流階級であったか、と問われれば、それは大いに違う、と答えなければならない。日本における,men of lettersは、たとえば農本主義を説いた安藤昌益、国学を説いた本居宣長、二宮尊徳、福沢諭吉然り。英国の文脈で言う上流階級というような存在ではなかった。本居宣長は、松坂で小児科医をしながら、4畳半の書斎で「古事記伝」を書き、将来自費出版するために竹筒貯金をしていたのだ。しかし、どんな時代にも、日本社会に賢人は存在した。つまり、民族として積み重ねてきた知性の質が違うと考えて良いのではないか。大英帝国の国家経営を模型にした資本主義経企業経営の模型を駆使して、しかしながら、戦後日本の企業は極めて一貫して、社員と出入り業者、つまり働く者のための企業であった。それは日本的というよりも、人間社会にとって、実に理想的な社会思想のあり方だったのだ。この時代には、多くの『代表的日本人』が生きていた。
ところが、バブル経済の時期を挟んで、ますます米国の手の内にはまり、「働きすぎ」、「努力する人のための社会に」などというスローガンとともに、簡単に言えば資本家のための企業社会に変質させられてきたのが、現在日本の企業風土である。日本の企業社会を、米国のファンド事業家の市場として解放させられた、その戦術として、企業家倫理に手をつけられた、政治家を使ってまんまとしてやられた、つまり、民族の思想の根幹に改変を求められて従った。
社会のインフラとしての余剰を、ごっそりと米国に浚われ続けてきた我が国に、目先の投資も覚束無いのに、決して出会うことのない遠い未来を生きる日本人のために、今から投資をする、それも、民族の言葉を作る投資に、まわす余剰はあるのだろうか。今や、それだけのmen of lettersは求められているだろうか。
私たちは、MedWet Initiativeとの連携によって、北東アジア湿原戦略構想会議NEA-Wet Initiativeの企画と運営を目指す。ギリシャで開催される会議にも参加することになるだろう。湿原を中心とした生態系保全、自然環境経営、その他、多くの課題を整理し、ひとつずつ、紐解いて行くことになる。北東アジアという、地政学上極めて不安定な地域の課題は、予測不可能だ。この課題は、当研究所を設立した当初から研究活動課題としてすでに確立していたが、ホフマン氏Dr Luc HoffmannとThe Tour du Valatとの出会いは、象徴的な出来事となった。この事の次第が、次にどんな事の次第に展開していくものか・・・
実のところ、私も辻井達一先生も、7月3日にルーマニアのブカレストに到着するまで、Dr Luc Hoffmannのことも、The Tour du Valat地中海湿原研究所のことも、ほとんど何も知らなかった。カマルグ湿原には、たしかに当初から旅をする予定だった。曽根一理事(現代表理事)とイタリアへ向かうことになって、予定していたウェールズの代替技術研究所Center for Alternative Technologyへの旅をキャンセルすることになり、さて、一般社団法人湿原研究所が目指す方向はCATではなさそうだとは、理解した。それでは何処に向かうのか、事の次第に対する読みを誤らぬように、慎重に対処するように、それだけを心掛けて旅の時間を過ごしていた。アヴィニョンの駅で、「心して行け」と脳理にささやくお告げがあった。沈思して、湿原研究所設立の趣旨を、Dr. Luc Hoffmann氏、Directeur General Jean JALBERT氏と、Programme Director Patrick GRILLAS氏に伝え、姉妹関係の確立と共同研究の意志を議論したのだ。
辻井達一先生は、そのように説明する私の話を、ニコニコしながら聞いておられた。そして少し興奮気味に話された。
「水田技術供与について提案したのは良かった。もらうばかりではなくて、こちらから湿原技術としての水田技術を西洋に供与するというのは良い案だ。この機会を使って、色々なことができるよ」
The Tour du Valatとの共同研究を含む国際共同研究事業は、遺志を継いで推進し、できるだけ若者に、新しい体験と研究の機会を与えられるように、態勢を整えていきたい。
湿原研究所は、平成23年4月より毎月第3木曜日の夕方から「柏林講座」と題した読書会を継続している。平成24年4月に研究所を設立してからは、毎月第3土曜日と翌日の日曜日にかけて「晩成学舎」と題した研究会を開催している。
平成24年8月17日から3日間は、十勝海岸湖沼群のは晩成温泉原生花園を借りて「晩成学舎特別講座」を開催した。
まず、8月17日午後3時より、大樹町生涯学習センター内オークホールにおいて、「辻井達一ラムサール賞受賞記念講演会」を開催した。後援は、忠類農業協同組合、十勝毎日新聞社、北海道ガーデン街道協議会。午後3時から私こと白井隆所長が「北海道湖水地方の現在と未来」と題して、当研究所と大樹農社による北海道湖水地方事業の概要を説明。
3時15分からは、林克彦北海道ガーデン街道協議会会長による「イギリス・ドイツ・日本」。旭川から南下するガーデン街道は、北海道湖水地方によって十勝南端に達し、そこから東に向かって釧路湿原、霧多布等を経て知床に向かう観光街道構想を披露した。
檀上で挨拶をする辻井達一先生
その後、去る7月6日にルーマニアのブカレストで開催されたラムサール会議において、ラムサール賞受賞式の模様を収めた、8分間のビデオ映像を上映。
十勝毎日新聞社会長でもあり、当研究所副会長を務める林光繁が5分間のスピーチを行った後、辻井達一先生の記念講演があった。参加者は約70名。
晩成温泉ロッジ前で夕食懇親会が開かれた。食事はとかち村ビストロコムニによるケイタリング。
18日朝6時。左手はホロカヤントー。晩成原生花園を出て、砂州を歩き、海岸段丘上へ向かう。
18日朝は、6時からエクスカーションを兼ねた戸外での朝食。
ホーストレッキング道を試す目的で、相田一家と蛭川徹先生が、朝食後、馬で当縁湿原に向かった。
左端が蛭川徹先生。
4頭の馬は当縁湿原の砂州に向かった。
朝食後は、再び晩成原生花園へ。
カワラナデシコの群落。7月にはもっと見事な花盛りだったはずだ。
矢部和夫札幌市立大学教授による植生解説を聞きながら、片道1時間かけてゆっくり歩いた。
野生のマツムシソウを発見。
矢部和夫教授
9時には原生花園に戻り、温泉に入るなど、参加者は休息を取った後、10時から新庄久志釧路国際ウェットランドセンター主幹による、「道東総合自然調査のこと」と題したセミナー、午後1時半からは、野田哲治浜中町農協酪農研究所研究員による「人工湿地による家畜のし尿処理技術」、その後、4時から辻井達一先生による「湿地のワイズユース」というセミナーを聞いた。
『マコモというワイルドライス、エゾカンゾウ、ブルーベリー、ふな鮨、アカエゾマツ、宍道湖の七珍、北海道の飯寿司に発展したニシン漬け、生ガキに垂らすアイラ島ウイスキーなど、湿地にまつわる食の話。
熱気球を使った観光で25.000円のお金をもらう観光商売の話。北海道湖水地方の場合は、飛行船はどうだろうか・・・・』
北海道湖水地方には、大樹町の航空公園があり、飛行船用の格納庫がある。うまく活用できれば、空から湖水地方を探索する観光企画が可能になるだろう。宿に迎えに行き、飛行船を用意する間、お茶とお菓子を楽しんでいただく。飛行船で2時間ほど湖水地方の全体を遊覧する。たとえば、レストランの近くに降り立って、観光客にはシャンパンを供して無事を喜んでいただく。そして、昼食を楽しむ。迎えが来て、宿に帰る。そんなプログラムは可能だろう。飛行船の操縦免許など、課題は多々あるが、湖水地方にはふさわしい案だ。
翌日19日朝の「戸外での朝食 エクスカーションを兼ねて」は、6時に宿舎の原生花園を出発。まず、生花湖畔の野鳥観察小屋付近の湖畔に出た。生花湖は、直径5センチくらいのシジミ漁で有名で、最近は、漁獲高が減り、一年に一日だけの漁を行って、築地市場などに出荷している。
シジミは砂質土に生息するので、おそらく酪農汚水の流入により、砂の上にヘドロが堆積しているのだろう。また、流入する河川上流の森を伐採して草地にしたことも、大きな原因だ。浜中町でも同じ課題があり、漁民と農民が協議会を設立。対策を検討しているが、酪農家の意識も少しずつ高まって、自発的に農地に植林を行うようになったと、野田哲治浜中町農協酪農研究所研究員から説明があった。
生花湖畔
生花湖を見下ろす牧場で朝食。あいにくの霧だったが、少しずつ晴れていった。
室瀬秋宏日本野鳥の会十勝支部長による、この地域の野鳥の説明があった。
8月19日晩成学舎最終日の閉会式で、辻井達一先生が、「基礎研究をやるべきだ」と力説されたのを受けて、北海道湖水地方の総合自然調査の準備を開始した。
十勝千年の森で
一か月ぶりにお目にかかった9月の湿地学会で、辻井達一先生はずいぶんお痩せになった。会場として借りた東京農大の食堂で珍しく黙っておられるから、「どうしました」とお聞きすると
「大学受験の時に東京農大も受験したんだ。ここに入学していたら、どんな人生だったかなと思ってね」
と、お答えになった。その時、9月末に検査入院する予定を聞いた。
10月10日、入院先の病院から許可をもらって、NHKカルチャーセンターの仕事で、十勝千年の森に来ると連絡があったので、出かけて行った。
「実は前立腺癌なんだよ」と、辻井達一先生がおっしゃった。
私の義父が同じ病気だったが薬を飲んで対処し、天寿を全うしたので、そう申し上げた。
11月9日、北海道新聞文化賞学術部門の受賞式が、札幌グランドホテルにて行われた。「学術部門 湿原の植物生態学研究と湿地保全への貢献」が受賞理由であった。
辻井達一先生の挨拶を要約すると、以下の通り。
「若き日に教授からサロベツ原野の研究をするように言われた。サロベツ原野では、泥炭地を開拓するために悪戦苦闘していた人々の姿が、今も脳裏を離れない。国の方針が変わり、じきに利用開発から保全に転換した。湿原は奥が深くて面白いと思った。
北海道の湿原では、これは日本人の情念とでもいうべきかもしれないが、人は泥炭地を改良して、稲作をしたいと情熱を注いできた結果、今では日本を代表する米作地帯になった。湿原の保全について、これまでは、世界の事例から学んできたが、今年の7月に南フランスの水田地帯を見て、日本の稲作の技術が、湿原活用の事例として、これからは世界に貢献できると考えるようになった。黒竜江省の水田も同様だ。これからの人生の時間を、その事業に費やしたいと考えている」
11月21日水曜日、釧路プリンスホテル。16時半より、釧路国際ウェットランドセンターが用意した、「辻井達一先生 瑞宝小綬賞受賞 ラムサール湿地保全賞受賞記念講演会」が開催された。
三膳時子認定NPO法人霧多布湿原トラスト理事長と、辻井達一先生
釧路湿原関係の方々が大勢集まったが、認定NPO法人霧多布湿原トラストの三膳 時子理事長が、実に堂々とお祝いのあいさつを述べ、辻井達一先生がほのぼのと嬉しそうにその姿を眺めていたのが、強く印象に残った。
また、今年八月に当研究所主催「晩成学舎特別講座」に講師としてご参加いただいた、辻井達一先生の弟子、新庄久志釧路国際ウェットランドセンター主任技術委員は、辻井達一先生の一代記を準備し、スライドで上映。辻井、新庄の両氏が解説するという趣向で、会場を大いに沸かせた。
右が新庄久志氏。
閉会後、ホテルのバーで、ラムサールセンターの武者孝幸氏を交えて歓談。30年以上、地域振興に従事してきた武者氏から、様々な忠言をいただいて、大いに勉強になった。右側が、武者孝幸ラムサールセンター副会長・ジャーナリスト。武者氏は辻井達一先生を「ご隠居」と呼び、辻井達一先生は武者氏を「海に千年 山に千年」と冗談を言う。NGOという公共には、実に多様な人間性を許容する「遊び」がある。
翌22日朝、辻井達一先生が、「実は、具合が悪いんだ」とおっしゃった。
「それでは、今日の予定はやめて、釧路駅から特急に乗って札幌に戻ってください」
と申し上げたが、
「いや、この仕事はやる。だが、夜の懇親会は辞退したいんだ。」
「無理なさることはありません。役所にラムサール条約について説明するのは、環境省の役人にやらせましょう」
しかし、辻井達一先生は強くおっしゃった。
「こういうことは、実情を知っている私みたいな人間が話した方が、ご理解いただけるものだ。説得するということは、とても大切なことだから。とにかく今日はやるよ・・・夕方、帯広駅まで送ってくれますか」と。
朝8時半に釧路を離れて、車で十勝方面へ。
一般社団法人湿原研究所設立後、辻井達一先生と十勝海岸湖沼群を歩いたのはこれが最初で最後になった。
十勝には、環境省が指定するラムサール条約潜在登録湿地が2か所ある。十勝川流域湿地群と、十勝海岸湖沼群だ。十勝川流域湿地群は、池田町、豊頃町、浦幌町に展開し、十勝海岸湖沼群は、大樹町と豊頃町、そして幕別町忠類に広がっている。十勝平野の東と南が、wetlands。豊頃町は、この両者に属している。
辻井達一先生とともに、こちらから、自治体に対して話したことは、以下の四点。
1.今年のラムサール会議の議題は、湿原観光/wetlands tourism。ラムサール会議では湿地を資源としてとらえて、賢明な利用/wise useを推進し、その利用の内容を吟味することで、自然環境と人間の相互発展関係を築くという考えである。ツーリズムというのは、かつての大量消費型観光ではなく、農山漁業から特産品の開発、エコツーリズムまで視野に入れたものだ。湿原保全のために、湿原をいかに活用するかが現代の課題である。
2.現在環境省が指定している、約500の潜在候補地を選定した経緯。ラムサール条約が定義するwetlandsが実に豊かに存在する日本では、少なくとも500は指定したいと環境省は考えた。環境省にはその思いが強く、指定した当時、自治体に対する説明をせずに、学者を集めてリストを作って発表してしまった結果として、地元は蚊帳の外に置かれることになった。一つずつ説明に歩いていると、膨大な時間がかかると考えたからだろう。しかし、来年から環境省も、湿地保全の重要性とラムサール条約の意義を各自治体に説明する作業を数年かけて行うはずだ。
3.今後、ラムサール会議の理念と条約の意味などを勉強する会を連携して開催したい。また、ラムサール条約登録湿地には、独自な調査資料があるべきだが、過去に調査資料がなくはないが、古いということと、この地域独自なものではない。今後、各自治体の議論の基礎になるような総合調査を行って、報告書にまとめたい。その作業の過程で、各自治体間の連携を深めたい。
4.ラムサール条約登録を実現して、特に若者に、今後、継続的にラムサール会議に出席させたい。ラムサール会議という国際会議に参加することで、地元地域の課題という視点と、もう一つ、地球的な課題と議論という視点を持つことができる。若者が複眼的な視点を持つということは、今後の北海道十勝にとって、長い意味でとても大きな資産となるだろう。
浦幌町、豊頃町、大樹町、幕別町、十勝振興局と歩き、ラムサール条約会議が、地域の振興を真剣に論じていることを必死に説いた。だが、ラムサール条約に関する情報は、どの役所のスタッフも、まったく持っていなかった。「これは、正式な説明会を開く必要があるな・・・」と、辻井達一先生は言われた。前日の釧路講演会で、主催者が辻井達一先生の言葉を紹介していた。「科学者というものは、自分の研究の成果を、社会のために役立てなければならない」
日が暮れた帯広駅で、見送りを断って駅舎に向かって歩いていく後ろ姿が、私が拝見した辻井達一先生の最後の姿であった。
2009年に大樹町字芽武に入植し、2010年に辻井達一先生と初めてお目にかかった。2012年4月に一般社団法人湿原研究所を作り、辻井達一先生に初代代表理事に就任していただいた。ほんの数年の時間だったが、この人物から何かを掴み取ろうと必死だったが、亡くなってみて、その存在の大きさを思い知らされた。今年の1月に逝去の報せを新庄さんから電話でいただき、絶句して何もできなくなった。
今、研究所の活動2年目に入り、私たち自身の指針を築く必要を痛感している。結局のところ、人間の知恵を磨き、少しでも進化させて、人と自然との折り合いをつけるために貢献すること、この一点に尽きるのではないか。
一般社団法人湿原研究所は、辻井達一先生逝去を受けて、曽根一氏を第二代代表理事に選任した。理事会も刷新する。この春、北海道環境財団、北海道コカ・コーラボトリング、北海道、前田一歩園、富士通などの研究助成を受けて、十勝海岸湖沼群の総合自然調査に着手。地元の人々と、タイキ・フローラと題した、植物相の調査を開始した。懸案の国際共同研究は、JICAの協力を得て推進している。また、十勝海岸湖沼群の地域経営の要として、辻井達一先生の案である地中海水牛乳によるチーズ事業に、研究機関として連携する。wetlands研究機関として、辻井達一先生が各所から届けて下さった資料を中心としたアーカイヴの整備を開始、『辻井達一記念アーカイヴ』と命名した。また、文部科学省の機関認定を受けて科研費申請の資格を取得済み。公益法人化の準備に着手するなど、財政上の基礎体力をつける。
これまでの数年間は、辻井達一先生の許容量の大きさを頼って、研究所の未来の企画を立案する時間であった。今後は、その可能性を形にしていくことになる。私たち一人一人の心の中では、これからも『辻井達一との対話』が続く。これが、辻井達一先生が遺された最大の遺産である。
一般社団法人湿原研究所 所長 白井隆